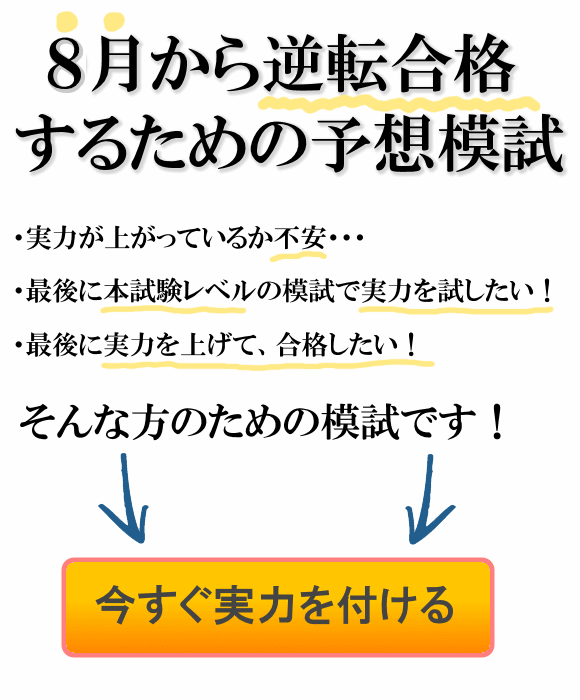Aを売主、Bを買主として、令和2年7月1日に甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.甲土地の実際の面積が本件契約の売買代金の基礎とした面積より少なかった場合、Bはそのことを知った時から2年以内にその旨をAに通知しなければ、代金の減額を請求することができない。
2.AがBに甲土地の引渡しをすることができなかった場合、その不履行がAの責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、BはAに対して、損害賠償の請求をすることができる。
3.Bが売買契約で定めた売買代金の支払期日までに代金を支払わなかった場合、売買契約に特段の定めがない限り、AはBに対して、年5%の割合による遅延損害金を請求することができる。
4.本件契約が、Aの重大な過失による錯誤に基づくものであり、その錯誤が重要なものであるときは、Aは本件契約の無効を主張することができる。
【答え:2】
1・・・誤り
本肢は「2年以内にその旨をAに通知しなければ」としているので誤りです。
引き渡された売買目的物が「種類又は品質」に関して契約の内容に適合しないときは、不適合を知った時から1年に、買主は売主への通知しなければなりません。(=期間制限のルール)
本肢は、面積不足(数量不足)なので、「数量」に関して契約不適合があります。
よって、上記「期間制限のルール」は適用されません。
そのため、1年内に通知をする必要はなく、通常の消滅時効期間である「不適合を知った時から5年」かつ「引渡しから10年」以内であれば責任追及が可能です。
2・・・正しい
①売主Aの責めに帰することができる事由(売主Aの責任が原因)で、Aが履行できなかった場合は、買主Bは、売主Aの債務不履行を理由に損害賠償請求ができます。
②一方、売主Aの責めに帰することができない事由(売主Aの責任でない原因)であれば、BはAに対して損害賠償請求はできません。
よって、本肢は正しいです。
本肢は問題文が難しいので、問題文の理解については、個別指導で解説します!
3・・・誤り
遅延損害金について、契約等で特段定めのないときは、遅延損害金の利率は「法定利率」が適用されます。
そして、法定利率は3%(3年ごとに1%単位で見直し)です。
よって、本肢は「5%」が誤りです。
4・・・誤り
意思表示に錯誤があり、その錯誤が重要なものである場合、錯誤を理由に取消しを主張することができます。
しかし、表意者Aに重大な過失があると、原則、取消しを主張することができません。
よって、本肢は「無効」は明らかに誤りです。
ただし、これを「取消し」に変えたとしても、表意者Aに重大な過失があるので、原則、取消しを主張することはできません。
詳細解説は個別指導で解説します!
令和2年(2020年)12月試験分:宅建試験・過去問
- 問1
- 不法行為
- 問2
- 代理
- 問3
- 親族
- 問4
- 債務不履行
- 問5
- 時効
- 問6
- 転貸借
- 問7
- 売買契約
- 問8
- 相続
- 問9
- 地役権
- 問10
- 共有
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 登録免許税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 業務上の規制
- 問27
- 広告
- 問28
- 媒介契約
- 問29
- 業務上の規制
- 問30
- 保証協会
- 問31
- 免許
- 問32
- 35条書面
- 問33
- 営業保証金
- 問34
- 報酬
- 問35
- 37条書面
- 問36
- 業務上の規制
- 問37
- 37条書面
- 問38
- 宅建士
- 問39
- クーリングオフ
- 問40
- 業務上の規制
- 問41
- 業務上の規制
- 問42
- 35条書面
- 問43
- 宅建士
- 問44
- 宅地の定義
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物