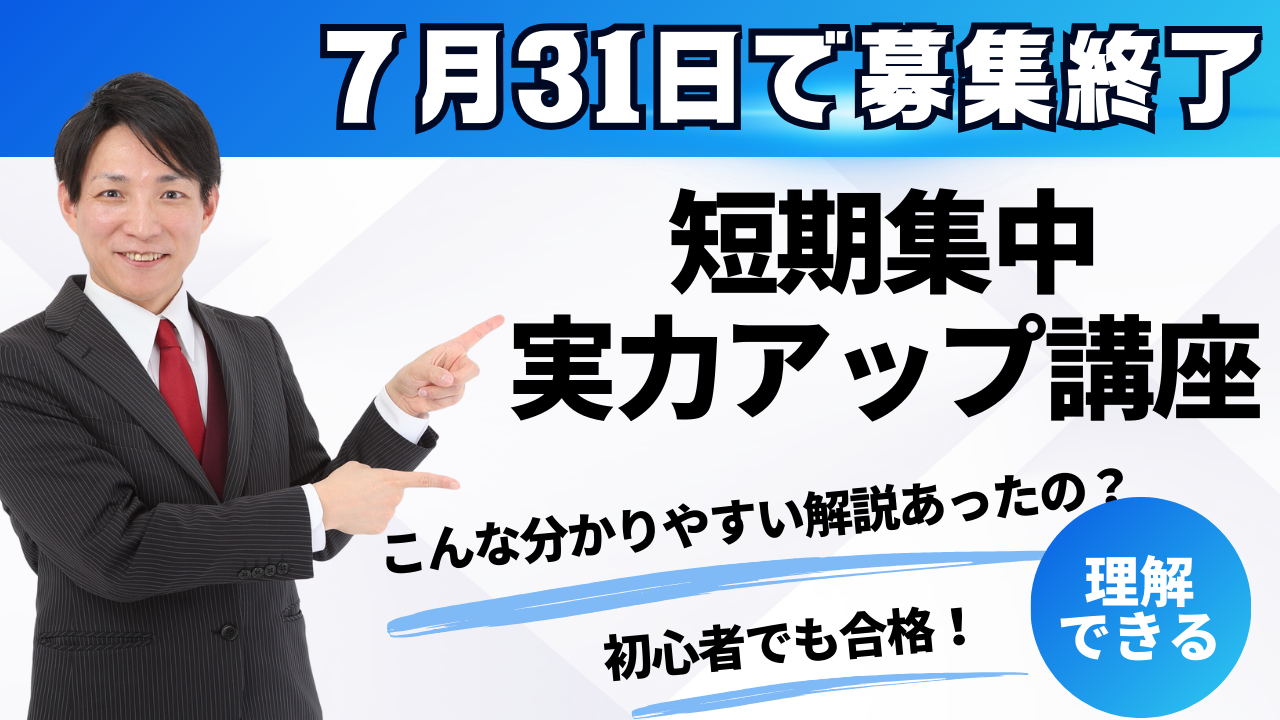宅地建物取引業者Aが自ら売主となる売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1.宅地建物取引業者でない買主Bが、法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフについてAより書面で告げられた日から7日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、9日目にAに到達した場合は、クーリング・オフによる契約の解除をすることができない。
2.宅地建物取引業者でない買主Cとの間で土地付建物の売買契約を締結するに当たって、Cが建物を短期間使用後取り壊す予定である場合には、建物について、一切担保責任を負わない旨の特約を定めることができる。
3.宅地建物取引業者Dとの間で締結した建築工事完了前の建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を代金の額の30%と定めることができる。
4.宅地建物取引業者でない買主Eとの間で締結した宅地の売買契約において、当該宅地の引渡しを当該売買契約締結の日の1月後とし、当該宅地の契約不適合に関する通知期間について、当該売買契約を締結した日から2年間とする特約を定めることができる。
【答え:3】
1・・・誤り
クーリングオフができなくなるのは、「書面で告げられた日から8日経過したとき」ですね!そして、 クーリングオフの効果は、買主が書面を発信したときに発生します。本問では、解除書面の発送を7日目に行っているので、この時点でクーリングオフができています! 到着日が9日目であっても関係ありません! ただ、本問は問題文の読み取りが非常に難しくなっています。
それに気づいていますか?
上記のように答えて終わる方もいますが、それだけだと、本試験で失点する可能性があります! 理解学習の話になるので、「個別指導プログラム」で解説しています!
2・・・誤り
売主が宅建業者、買主が宅建業者でない場合において「担保責任に関する特約」をする場合、契約不適合に関する通知期間を引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、民法の規定より買主に不利となる特約をすることはできません。本問は、「担保責任を負わないとしている」ので、民法の担保責任のルールに反しています。 したがって、本特約は無効です。したがって、誤りです。この問題は非常に重要な問題です。
①問題文を理解できるか?
②民法の契約不適合責任のルールとは何か?
この2つはしっかり押さえた上で答えを導く必要がります。(答えを覚えても意味ないですよ、、、) このような理解学習については「個別指導プログラム」で解説します!
このように、理解しながら学習しないと本試験では得点できないので、理解しがら学習を進めていきましょう!
3・・・正しい
宅建業者間の取引の場合、8種制限は適用されません。つまり、「自己所有に属しない物件の売買契約締結の禁止」のルールも「損害賠償額の予定等」のルールも適用されません。本問の買主Dは宅建業者なので、未完成物件の売買契約の締結もできるし、また、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う「損害賠償の予定額+違約金(合計額)」が代金の額の10分の2を超えても違反ではありません。したがって、本問は正しいです。
この問題でしっかり理解すべき部分は「自己所有に属しない物件の売買契約締結の禁止」と「損害賠償額の予定等」に関する内容でしょう!「個別指導プログラム」ではこの点を詳しく解説しています。単に問題を解けるだけでなく、本試験で得点できるように解説します!
4・・・誤り
売主が宅建業者、買主が宅建業者でない場合、契約不適合責任については、原則として民法の規定より買主に不利となる特約をしてはいけません。ただし、契約不適合に関する通知期間については、目的物の「引渡し」の日から2年以上となる特約はOKです。本問は、「契約締結」から2年となっています。この点が誤りです。
多くの方が、単に言葉が違っているから×とするのですが、そんなに薄い問題ではありません。実際は意味深い問題です。 もちろん、単純に言葉が違うからという理由で答えても正解します。
でも、それでは本試験のヒッカケ問題に対応できず落ちます。 そのため、「個別指導プログラム」では理解すべき部分を細かく解説しています! しっかり理解をして合格力を付けましょう!
平成27年度(2015年)宅建試験・過去問
- 問1
- 民法の条文
- 問2
- 通謀虚偽表示
- 問3
- 賃貸借と使用貸借
- 問4
- 取得時効
- 問5
- 占有
- 問6
- 抵当権
- 問7
- 抵当権の処分
- 問8
- 同時履行の関係
- 問9
- 転貸借
- 問10
- 相続
- 問11
- 借家権
- 問12
- 定期借家権と普通借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法(開発許可)
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 建築基準法(建築確認)
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 国土利用計画法
- 問22
- 農地法
- 問23
- 相続時精算課税制度
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 宅地建物取引業の定義
免許の要否 - 問27
- 免許の基準
- 問28
- 媒介契約
- 問29
- 重要事項説明
- 問30
- 媒介契約
- 問31
- 35条書面の記載事項
- 問32
- 35条書面の記載事項
- 問33
- 報酬計算
- 問34
- 8種制限
- 問35
- 宅地建物取引士
- 問36
- 8種制限
- 問37
- 業務上の規制
- 問38
- 37条書面
- 問39
- 8種制限
- 問40
- 8種制限
- 問41
- 業務上の規制
- 問42
- 営業保証金と保証協会
- 問43
- 監督処分
- 問44
- 案内所
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計(省略)
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物




.gif)