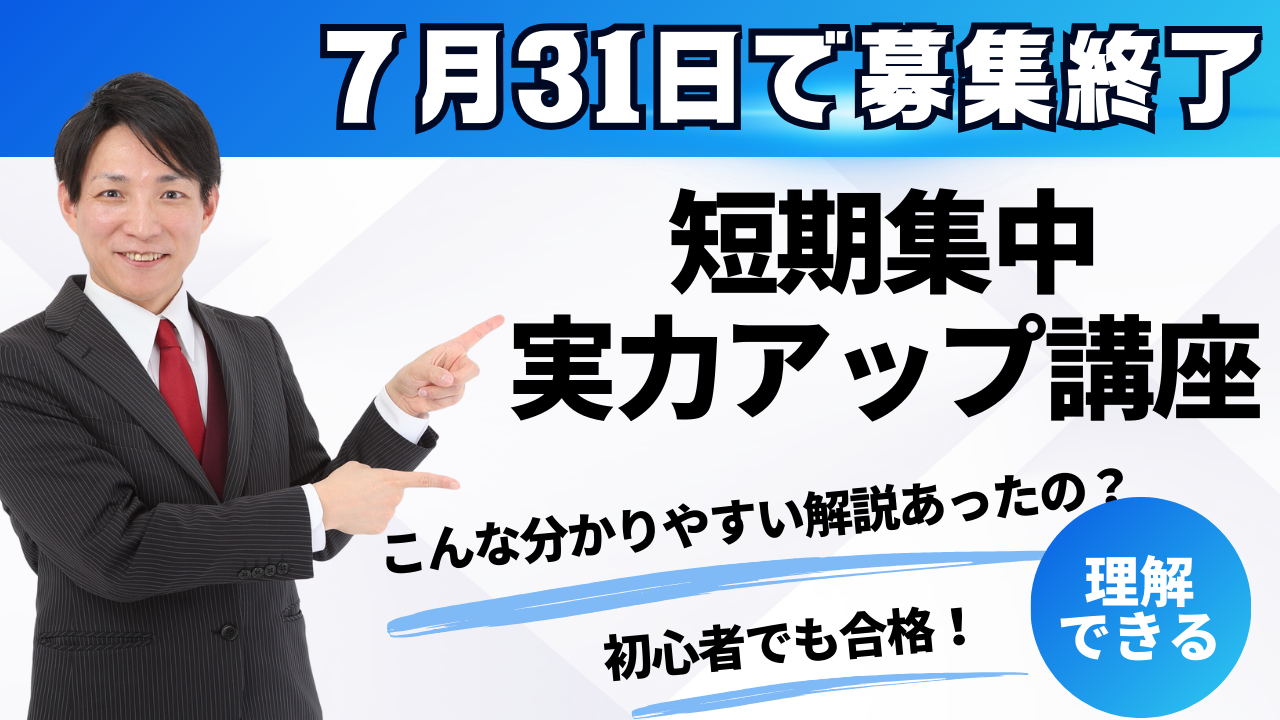宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることができる報酬についての次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.Aが、Bから売買の媒介を依頼され、Bからの特別の依頼に基づき、遠隔地への現地調査を実施した。その際、当該調査に要する特別の費用について、Bが負担することを事前に承諾していたので、Aは媒介報酬とは別に、当該調査に要した特別の費用相当額を受領することができる。
2.Aが、居住用建物について、貸主Bから貸借の媒介を依頼され、この媒介が使用貸借に係るものである場合は、当該建物の通常の借賃をもとに報酬の限度額が定まるが、その算定に当たっては、不動産鑑定業者の鑑定評価を求めなければならない。
3.Aが居住用建物の貸主B及び借主Cの双方から媒介の依頼を受けるに当たって、依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、借賃の1か月分の0.55倍に相当する金額以内である。ただし、媒介の依頼を受けるに当たって、依頼者から承諾を得ている場合はこの限りではなく、双方から受けることのできる報酬の合計額は借賃の1か月分の1.1倍に相当する金額を超えてもよい。
4.Aは、土地付建物について、売主Bから媒介を依頼され、代金300万円(消費税等相当額を含み、土地代金は80万円である。)で契約を成立させた。現地調査等の費用については、通常の売買の媒介に比べ5万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する旨、Bに対して説明し、合意の上、媒介契約を締結した。この場合、AがBから受領できる報酬の限度額は20万200円である。
【答え:1】
1・・・正しい
「依頼者からの特別な依頼」に基づいて、現地調査をし、この現地調査費用について、依頼者から事前に承諾を受けているのであれば、宅建業者は、媒介報酬とは別に現地調査費用を受領することができます。
これは勘違いしている人も多い部分なので、個別指導で詳細に解説いたします!
2・・・誤り
宅地や建物の使用貸借(無料で貸し借りをすること)の媒介では、借賃(賃料)がありません。
そのため、宅地や建物の使用貸借の媒介の場合の報酬は、「通常の借賃(通常の賃貸借の賃料)」で計算した媒介報酬額が上限となります。
この「通常の借賃」は、その宅地建物が賃貸借される場合で通常定められる適正かつ客観的な賃料を指すものであり、その算定に当たっては、必要に応じて不動産鑑定業者の鑑定評価を求めることとなっています。
つまり、本肢は「算定に当たっては、不動産鑑定業者の鑑定評価を求めなければならない」となっているので誤りです。必要がなければ不動産鑑定業者の鑑定評価を求めなくてもよいです。
3・・・誤り
居住用建物の賃貸借の場合、媒介業者が依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、原則、借賃の0.5か月分+消費税(=1か月分の0.55倍)が上限です。
ただし、例外として、媒介の依頼を受けるに当たって、依頼者から承諾を得ている場合は、依頼者から借賃の1か月分+消費税を上限に報酬を受領することができます。
また、依頼者の双方から受けることのできる報酬額の合計は、借賃の1か月分+消費税(=1か月分の1.1倍)を超えてはいけないとなります。
本肢は「双方から受けることのできる報酬の合計額は借賃の1か月分の1.1倍に相当する金額を超えてもよい」となっているので誤りです。
正しくは「双方から受けることのできる報酬の合計額は借賃の1か月分の1.1倍に相当する金額を超えてはいけない」です。
4・・・誤り
土地については消費税がかからないので、土地の代金は80万円です。
建物については、消費税がかかるので、220万円のうち20万円が消費税となり、建物の代金は200万円となります。
つまり、土地と建物の代金は合計して、280万円ということです。
【媒介報酬額の上限の計算】
代金が400万円以下なので、「400万円以下の特例」を使うことができます。
まず、普通に報酬額を計算します。
280万円×4%+2万円=132,000円
これに消費税10%を加えると
132,000円×11=145,200円
次に、「400万円以下の特例」を考えます。
本問では、「現地調査等の費用については、通常の売買の媒介に比べ5万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する旨、Bに対して説明し、合意の上、媒介契約を締結した」と書いてあるので、上記報酬額(145,200円)に現地調査費用(消費税を含めて55,000円)を加えて、報酬額を計算することができます。
すると、
145,200円+55,000円=200,200円
となります。
ただし、「400万円以下の特例」では、通常の報酬額に現地調査費用を加算して金額について、18万円+消費税=198,000円を上限とするルールになっています。
したがって、200,200円は、198,000円を超えているため、200,200円を受けることはできません。
受領できる報酬額+現地調査費用の上限は、198,000円です。
令和4年(2022年):宅建試験・過去問
- 問1
- 背信的悪意者(判決文)
- 問2
- 相続
- 問3
- 制限行為能力者
- 問4
- 抵当権
- 問5
- 期間
- 問6
- 賃貸借・使用貸借
- 問7
- 失踪宣告
- 問8
- 地上権・賃貸借
- 問9
- 辞任
- 問10
- 取得時効
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 印紙税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示
- 問26
- 事務所の定義
- 問27
- 報酬
- 問28
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問29
- 宅建士
- 問30
- 業務上の規制
- 問31
- 媒介契約
- 問32
- 契約書(37条書面)
- 問33
- 宅建士
- 問34
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問35
- 業務上の規制
- 問36
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問37
- 広告
- 問38
- クーリングオフ
- 問39
- 保証協会
- 問40
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問41
- 営業保証金・保証協会
- 問42
- 媒介契約(専属専任)
- 問43
- 8種制限
- 問44
- 契約書(37条書面)
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物




.gif)