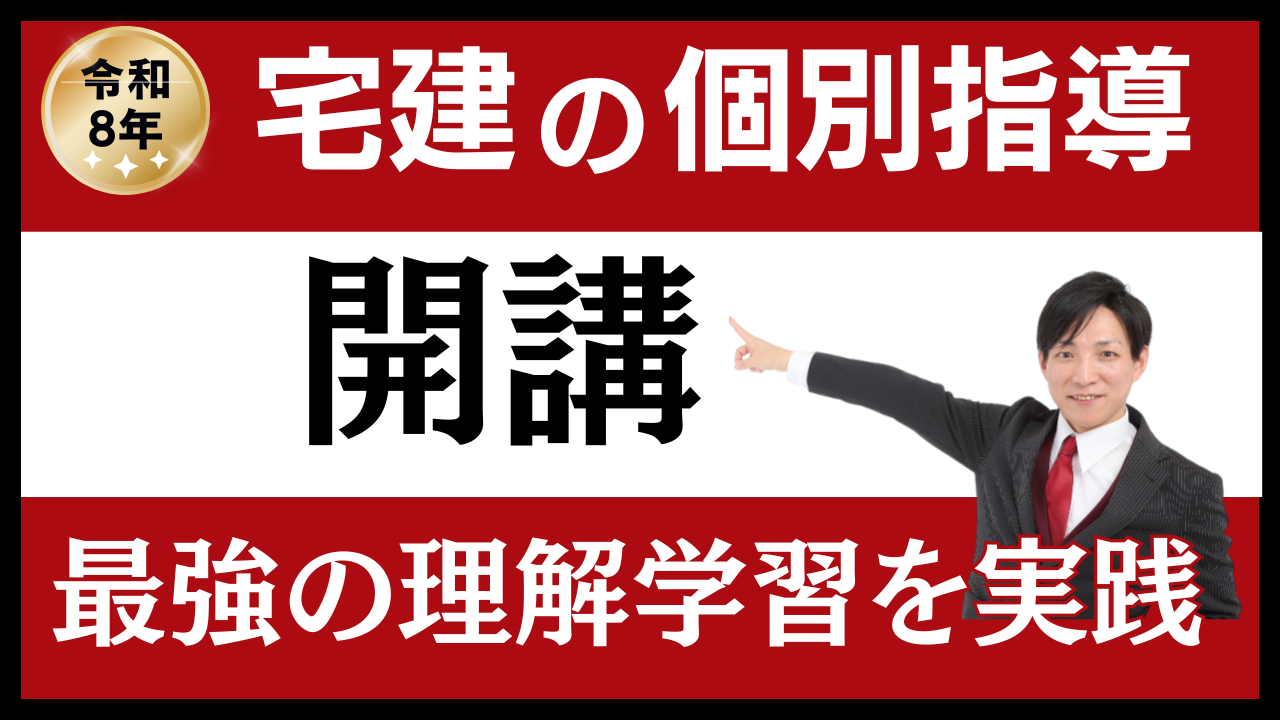Aは自己所有の甲建物をBに賃貸し賃料債権を有している。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Aの債権者Cが、AのBに対する賃料債権を差し押さえた場合、Bは、その差し押さえ前に取得していたAに対する債権と、差し押さえにかかる賃料債務とを、その弁済期の先後にかかわらず、相殺適状になった段階で相殺し、Cに対抗することができる。
2 甲建物の抵当権者Dが、物上代位権を行使してAのBに対する賃料債権を差し押さえた場合、Bは、Dの抵当権設定登記の後に取得したAに対する債権と、差し押さえにかかる賃料債務とを、相殺適状になった段階で相殺し、Dに対抗することができる。
3 甲建物の抵当権者Eが、物上代位権を行使してAのBに対する賃料債権を差し押さえた場合、その後に賃貸借契約が終了し、目的物が明け渡されたとしても、Bは、差し押さえにかかる賃料債務につき、敷金の充当による当然消滅を、Eに対抗することはできない。
4 AがBに対する賃料債権をFに適法に譲渡し、その旨をBに通知したときは、通知時点以前にBがAに対する債権を有しており相殺適状になっていたとしても、Bは、通知後はその債権と譲渡にかかる賃料債務を相殺することはできない。
【答え:1】
1・・・正しい
差押債権と相殺の関係では、反対債権を差し押さえる前に取得していたかどうかで判断します。
債務者Cは、債権者Bに対して差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができません。
差押え前から反対債権を有している場合は、その弁済期の先後にかかわらず相殺することができます。
2・・・誤り
抵当権に基づく差押と相殺の関係では、反対債権を抵当権設定前に取得していたかどうかで判断します。
債務者Bが取得したのは、Dの抵当権設定後なので、BはDが抵当権に基づいて差し押さえた債権と相殺することはできません。
3・・・誤り
敷金は、目的物の明渡し後に、賃料の不払等を差し引いて、残額を賃貸人から賃借人に返還されるものです。
Eが差押えているのは賃料についてです。
明渡し後であれば、賃料の不払いなどの残債がなければ、敷金は賃借人のものとなります。
一方、残債がある場合は、敷金が存在する限度で敷金の充当により当然消滅します。
よって、賃借人は敷金の充当による消滅を抵当権者に対抗することができる。
4・・・誤り
これは債権譲渡と相殺の問題です。
つまり、反対債権を取得したのが、譲渡通知の前なのか後なのかで優劣を判断します。
通知前にBは相殺適状であったわけなので、もちろん反対債権を取得していたということです。
なので、BはFに対して相殺を主張できます。
平成23年度(2011年)宅建試験・過去問
- 問1
- 詐欺、強迫
- 問2
- 停止条件
- 問3
- 共有
- 問4
- 根抵当権
- 問5
- 債権譲渡
- 問6
- 相殺
- 問7
- 転貸借
- 問8
- 契約関係
- 問9
- 契約不適合責任
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権・一時使用
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 国土利用計画法
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 開発許可
- 問18
- 防火地域
- 問19
- 建築基準上全般
- 問20
- 宅地造成等規制法
- 問21
- 土地区画整理法
- 問22
- 農地法
- 問23
- 印紙税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示
- 問26
- 宅地建物取引業の免許
- 問27
- 宅建業の欠格事由
- 問28
- 宅地建物取引業全般
- 問29
- 宅建士の登録
- 問30
- 営業保証金
- 問31
- 媒介契約
- 問32
- 重要事項説明
- 問33
- 重要事項説明
- 問34
- 35条書面と37条書面
- 問35
- クーリングオフ
- 問36
- 広告
- 問37
- 8種規制 総合
- 問38
- 手付金等の保全措置
- 問39
- 8種規制 総合
- 問40
- 報酬額の制限
- 問41
- 宅建業法 総合
- 問42
- 案内所
- 問43
- 宅地建物取引業保証協会
- 問44
- 監督処分
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物