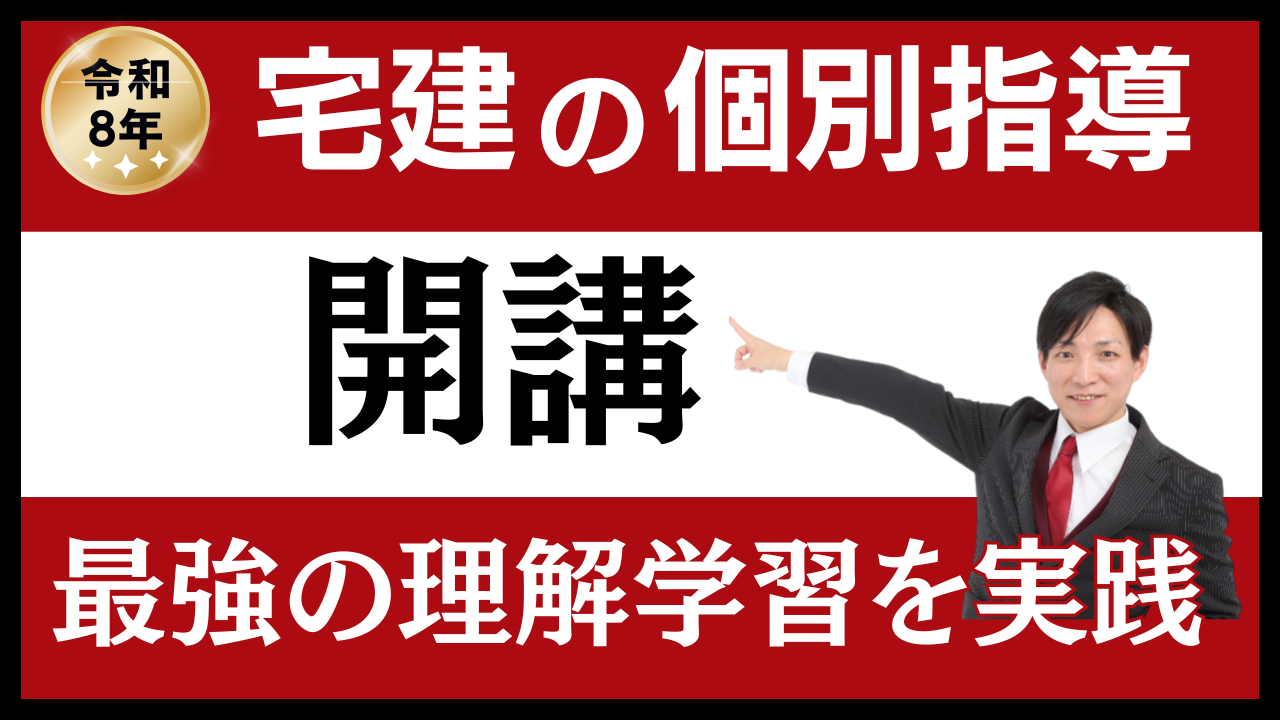Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため得意先に向かっている途中で交通事故を起こし、歩いていたCに危害を加えた場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1.BのCに対する損害賠償義務が消滅時効にかかったとしても、AのCに対する損害賠償義務が当然に消滅するものではない。
2.Cが即死であった場合には、Cには事故による精神的な損害が発生する余地がないので、AはCの相続人に対して慰謝料についての損害賠償責任を負わない。
3.Aの使用者責任が認められてCに対して損害を賠償した場合には、AはBに対して求償することができるので、Bに資力があれば、最終的にはAはCに対して賠償した損害額の全額を常にBから回収することができる。
4.Cが幼児である場合には、被害者側に過失があるときでも過失相殺が考慮されないので、AはCに発生した損害の全額を賠償しなければならない。
この問題は使用者責任の問題ですね!
A:使用者、B:従業員(被用者)、C:被害者
でBが営業中にCに危害を加えたという図式ですね。
【答え:1】
1・・・正しい
そもそも使用者責任とは、(外見からみて営業中に見える場合も含め)営業中に従業員(被用者)が第三者に危害を加えた場合、従業員だけでなく、使用者にも損害賠償責任が生じるという内容です。
そして、本肢は、従業員の損害賠償債務が時効になって消滅した場合、使用者Aの損害賠償債務も連動して消滅するか?という問いです。これは、消滅しません!
使用者責任における損害賠償債務は、連帯債務であり、さらに、相手方に債務を弁済する以外の事柄については、連帯債務者間で影響を及ぼしません。つまり、従業員の損害賠償債務が時効になって消滅しても、使用者の債務には全く関係しないということです。
そして、このように、連帯債務者間で影響を及ぼさないことを相対効といいます。
2・・・誤り
被害者が即死の場合であっても、被害者にも精神的な損害を観念することができ、被害者の慰謝料請求権について、被害者の相続人は相続することができます。
即死であっても、損害賠償責任は相続されるというポイントだけ覚えておきましょう。
3・・・誤り
被害者に対して全額を賠償した使用者は、被用者に対して「信義則上相当な範囲」で求償権を行使することができます。被用者に対して「常に全額」を求償できるとは限りません。
4・・・誤り
被害者が幼児で、被害者自身には過失がなくても、親のような保護者に過失がある場合は、過失相殺を考慮することができます。
判例では、被害者側の過失を考慮するといっており、親が被害者側に含まれるということです。
4は初出題で分からないかもしれませんが、その他は過去問で出題されています。 必ず得点すべき問題でしょう。
平成24年(2012年)宅建試験過去問集
- 問1
- 虚偽表示
- 問2
- 代理
- 問3
- 民法の条文
- 問4
- 表見代理
- 問5
- 請負
- 問6
- 物権変動
- 問7
- 物上代位
- 問8
- 債務不履行
- 問9
- 使用者責任
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 国土利用計画法(事後届出)
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 開発許可
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 建築基準法
- 問20
- 宅地造成等規制法
- 問21
- 土地区画整理法
- 問22
- 農地法
- 問23
- 譲渡所得
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価
- 問26
- 免許
- 問27
- 免許
- 問28
- 広告
- 問29
- 媒介契約
- 問30
- 重要事項説明
- 問31
- 37条書面
- 問32
- 35条書面と37条書面
- 問33
- 営業保証金
- 問34
- 手付金
- 問35
- 報酬
- 問36
- 宅建士
- 問37
- クーリング・オフ
- 問38
- 8種規制
- 問39
- 担保責任の特約制限
- 問40
- 宅建業法総合
- 問41
- 宅建業法総合
- 問42
- 案内所
- 問43
- 保証協会
- 問44
- 監督処分
- 問45
- 特定住宅瑕疵担保責任
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物