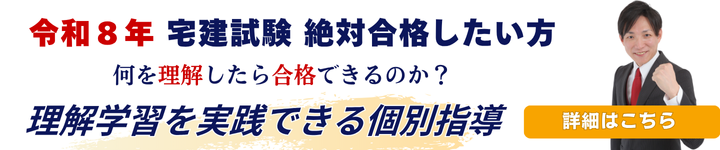はじめに
宅建試験では、「どの用途地域にどんな建築物が建てられるか」という問題が頻繁に出題されます。用途地域は、都市計画の観点から建築物の用途や規模を制限する仕組みであり、無秩序な土地利用を防ぎ、住環境の保護や地域の特性に応じた開発を促すために設けられています。
本テキストでは、法律の条文をそのまま使用しながら、具体例や図表を交えて、初学者でも理解できるように解説を行います。また、合格ステップという学習方法を用いて、重要な論点を段階的に整理する手法も紹介します。これからの解説内容をしっかりと身につけ、実際の試験問題に対応できるようにしましょう。
用途地域ごとの用途規制の基本的な考え方
用途地域は、市街地の秩序ある発展と住環境の保護を目的として、建築物の用途を地域ごとに区分・規制する制度です。用途地域ごとに「建築できる建築物」と「特定行政庁の許可がなければ建築できない建築物」が定められており、これにより、例えば住宅地には無秩序な商業施設が進出しないような仕組みが整えられています。
各用途地域における建築物の用途別規制の詳細解説
下表【表1】の最上部の行の用語を解説します。
- 一低専:第一種低層住居専用地域
- 二低専:第二種低層住居専用地域
- 田園住:田園住居地域
- 一中専:第一種中高層住居専用地域
- 二中専:第二種中高層住居専用地域
- 一住:第一種住居地域
- 二住:第二種住居地域
- 準住:準住居地域
- 近商:近隣商業地域
- 商業:商業地域
- 準工:準工業地域
- 工業:工業地域
- 工専:工業専用地域
「〇が建築できる」「✕が建築できない」という意味です。
| 建築物の用途 | 一低専 | 二低専 | 田園住 | 一中専 | 二中専 | 一住 | 二住 | 準住 | 近商 | 商業 | 準工 | 工業 | 工専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宗教施設、巡査派出所、診療所、保育所、幼保連携型認定こども園 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
| 老人ホーム、福祉ホーム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
| 図書館、博物館、美術館 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
| 小学校、中学校、高校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| 物品販売店舗・飲食店(2階以下かつ150㎡以内) | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
| 物品販売店舗・飲食店(2階以下かつ500㎡以内) | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
| 自動車車庫(2階以下かつ300㎡以内) | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 病院 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| 大学、高専、専修 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| 事務所 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 物品販売店舗・飲食店(1500㎡以内) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
① すべての用途地域で建築できる建築物
寺院・教会・神社などの宗教施設、巡査派出所・公衆電話所などの近隣公共施設、診療所・公衆浴場といった医療衛生施設、保育所に類する社会福祉施設、幼保連携がたにんていえん型認定こども園は、すべての用途地域において建築できます。
「寺院・教会・神社などの宗教施設、巡査派出所・公衆電話所などの近隣公共施設、診療所・公衆浴場といった医療衛生施設,保育所に類する社会福祉施設,幼保連携型認定こども園は、すべての用途地域において建築できます(48条1項13項、別表第二(い)項(わ))。」
たとえば、都市部や郊外で新たに教会や診療所を建設する場合、用途地域の区分にかかわらず建築が認められているため、規制面でのハードルが低く、安心して施設計画を進めることができます。
② 住宅及び関連施設
住宅は、住居系の用途地域での建築が基本ですが、意外なことに住宅は工業専用地域以外の多くの用途地域で建築可能です。
「住宅は住居系の用途地域において建築できるのは当たり前としても、他の用途地域でも意外と建築できる用途地域が多く、工業専用地域以外ならば、どの用途地域においても建築できます (48条13、別表第二(わ)項第2号、 3号参照)。」
マンションや一戸建て住宅は、第一種低層住居専用地域だけでなく、商業地域や田園住居地域でも建築が可能です。また、老人ホームや福祉施設、図書館・博物館・美術館なども同様の規制が適用され、用途に応じた多様な建築物が認められています(48条13項、別表第二(わ)項第4号、6号参照)。
③ 店舗・事務所
店舗や事務所に関しては、無秩序な事業進出を防ぐため、住居系の用途地域では厳しい規制が設けられています。
第一種低層住居専用地域の場合
店舗や事務所は、住宅に付属したもの、つまり兼用住宅としてのみ認められます。具体的には、住居部分が延べ面積の2分の1以上を占め、その上で用途部分(店舗、食堂、喫茶店、事務所など)が主たる目的として設定され、さらにその用途部分の床面積合計が50m²以内である必要があります。(48条1項、別表第二(い)項第2号、施行令130条の3)
第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域の比較
第一種低層住居専用地域で認められている建築物は、第二種低層住居専用地域でも建築可能です。ただし、第二種では、店舗・飲食店などの用途部分の床面積が150m²以内で、かつ2階以下の部分がその用途に供されるか否かが判断基準となります。(48条1項、2項、別表第二(い)項、(ろ)項第2号、施行令130条の5の2)
実際に、理髪店、美容院、クリーニング取次店、洋服店、畳屋、自転車店などは、この規定に基づいて、住宅に隣接する小規模な店舗として建築が認められています。
また、田園住居地域では、第二種低層住居専用地域と同様の基準に加え、500m²以内で、かつ2階以下の部分が地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗や、農業の利便性を向上させるための施設も認められています(建基法48条8項、別表第二(ち)、施行令130条の9の4)。
④ 学校
学校に関しては、用途地域によって建築が認められる条件が異なります。
工業地域および工業専用地域では、基本的に学校の建築は認められていません。しかし、住宅地としての利便性が求められる小・中・高等学校は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域においては建築が認められています。
一方で、大学などの大規模な教育施設は、敷地の広さや施設規模の観点から、これらの住宅系の用途地域では建築が認められない場合が多い点に注意が必要です。
⑤ 医療衛生施設
医療衛生施設は、診療所と病院とで建築可能な用途地域が異なります。
急な病気や怪我に対応するため、診療所はどの用途地域においても建築が認められています。
一方、病院は入院患者が多く、外来や救急車の出入りが頻繁であるため、工業地域や工業専用地域はもちろん、静かな住宅地域でも建築が認められない規制が設けられています。
| 建築物の用途 | 一低専 | 二低専 | 田園住 | 一中専 | 二中専 | 一住 | 二住 | 準住 | 近商 | 商業 | 準工 | 工業 | 工専 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工場(原動機を使用し、50㎡以内) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 物品販売店舗、飲食店(3000㎡以内) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | |
| 自動車教習所 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ボーリング場、スケート場、水泳場 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | |
| ホテル、旅館 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | |
| カラオケボックス | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| マージャン店、パチンコ店 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | |
| 物品販売店舗、飲食店(3階以上または10,000㎡以内) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | |
| 倉庫業を営む倉庫 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 自動車修理工場(150㎡以内) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 工場(原動機を使用し、150㎡以内) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 劇場、映画館(客席200㎡未満) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | |
| 劇場、映画館(客席200㎡以上10,000㎡以内) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | |
| 劇場、映画館、店舗、飲食店(10,000㎡超) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | |
| 料理店、キャバレー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | |
| 個室付浴場 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ |
⑥ 工場
工場については、規模や使用する機械の種類により、建築が認められるかどうかが異なります。
原動機(モーター)を使う小規模な工場で、床面積が50m²以内であれば、第一種・第二種低層住居専用地域でも建築が可能です。実際、町工場としての小規模な施設は、周辺住環境に大きな影響を及ぼさないことから、住居系の用途地域においても一定の容認がされています。また、住環境保護の観点から、準住居地域では150m²以内の自動車修理工場が建築可能とされている点も覚えておきましょう。
⑦ 料理店
料理店は、客を接待し飲食を提供する施設であり、風俗営業施設に分類されます。
料理店は、キャバレーなどと同様に、周囲住民の生活環境に影響を与える可能性があるため、商業地域および準工業地域に限定して建築が認められています。一般の飲食店と混同しないよう、用途規制の内容を正確に把握することが求められます。
⑧ 準工業地域に建築できない建築物
準工業地域は、比較的規制が緩やかな地域ですが、例外的に建築が認められない建築物も存在します。
例えば、個室付浴場は、商業地域においてのみ建築が認められており、準工業地域では建築が制限されています。
⑨ 用途地域の指定のない区域に建築できない建築物
これは、表には載っていないのですが、用途地域の指定がない区域(市街化調整区域を除く)では、原則として用途規制はありませんが、近年、郊外などで大規模な店舗やアミューズメント施設等の進出により無秩序な土地利用が問題視されるようになりました。
「用途地域の指定のない区域においても、その用途に供する部分の床面積の合計が10,000m²を超える店舗、飲食店,展示場,遊技場等、客席部分の床面積の合計がてんじょうゆうこう きゃくせき 10,000m²を超える劇場、映画館、演芸場等は、原則として建築できないこととなりました (48条14項、別表第二(か)項)。」
その他の用途規制
用途地域による規制のほか、特定の施設や地区に対しては、別途規制が設けられています。
(a) 卸売市場・火葬場・汚物処理場等
卸売市場、火葬場、汚物処理場等は、立地する場所が近隣住民にとって好ましくない上、大型設備であるため、都市計画においてその敷地の位置があらかじめ定められていない場合、原則として新築または増築が禁止されています。(51条)
(b) 特別用途地区内の用途規制
特別用途地区は、用途地域の指定を補完するために設定される地区です。
「特別用途地区は、用途地域の指定を補完して定める地区です(合格ステップ7参照、46頁)。そこで、その地区の指定の目的のために建築物の建築の制限又は禁止に関し必要な規定を、地方公共団体の条例で定めることができます (49条 1項)。また、地方公共団体は、必要な場合には、国土交通大臣の承認を得て、条例で、用途制限を緩和することができます(49条2項)。」
さらに、市町村は地区計画の区域内において、国土交通大臣の承認を得た上で建築基準法の用途制限を緩和することが可能です(68条の2)。
(c) 居住環境向上用途誘導地区内の用途規制
居住環境向上用途誘導地区内では、地方公共団体が国土交通大臣の承認を得て、条例により用途地域の規制を緩和できる仕組みが設けられています。(60条の2の2)
この規定により、住環境の向上を図りながら、地域の実情に合わせた柔軟な運用が可能となっています。
敷地が用途規制の異なる地域にまたがる場合の取扱い
敷地が複数の用途地域にまたがっている場合、どの用途規制を適用するのかという疑問が生じます。この場合、原則として建物の敷地の過半数を占める地域の規制が適用されます。
敷地の総面積が200m²あり、そのうち120m²が第一種低層住居専用地域、80m²が第二種低層住居専用地域に属しているとします。この場合、200m²全体については、過半数である第一種低層住居専用地域の用途規制が適用されます。(91条)
このルールは、敷地全体の管理や計画を一律に判断するための重要な基準となっています。