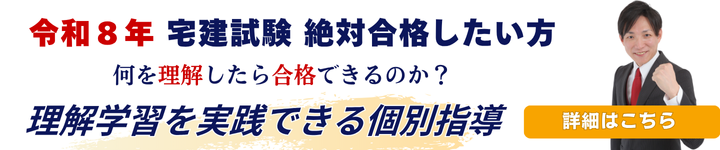第一種・第二種低層住居専用地域等の外壁後退距離の限度
第一種・第二種低層住居専用地域及び田園住居地域は、静かで落ち着いた住環境を守るための地域です。そのため、家と家の間隔をしっかり確保することが求められます。
そのため、都市計画法(都計法)では、これらの地域において 「外壁の後退距離の限度」 を設定できると定めています(都市計画法8条3項2号)。
外壁の後退距離とは?
これは、家を建てる際に「敷地の境界線から建物の外壁まで、最低限確保しなければならない距離」のことを指します。都市計画で外壁後退距離が定められた場合、 1.5mまたは1m の距離を空けなければなりません(都市計画法54条1項、2項)。
具体例
たとえば、Aさんが第一種低層住居専用地域に家を建てるとします。この地域では、都市計画で「外壁の後退距離は1.5m」と定められていました。この場合、Aさんの家の外壁は 敷地境界線から1.5m以上 離して建てる必要があります。
この規制によって、家と家の間隔が確保され、プライバシーが保たれるだけでなく、採光や通風の確保にも役立ちます。
ポイント
第一種・第二種低層住居専用地域及び田園住居地域では、都市計画で 外壁の後退距離の限度 を定めることができる。
後退距離は1.5mまたは1m。
都市計画で定められた場合、建築物の外壁は その距離以上、敷地境界線から離して建築する必要がある。
壁面線の指定による建築制限
通常、建物は自分の敷地内であれば自由に配置できます。しかし、それでは街並みがバラバラになり、統一感のない景観になってしまいます。
そこで、特定行政庁(市区町村の役所など)は、 街区内の建築物の位置を整え、美しい街並みを作るために 「壁面線」を指定することができます(建築基準法46条1項)。
壁面線とは?
壁面線とは、 建物の壁を揃えるためのライン です。このラインを超えて建物を建てることは原則としてできません(建築基準法47条)。
具体例
B市では、新しい住宅街を開発するにあたり、「道路から3mの位置に壁面線を設定する」と決めました。すると、そこに家を建てるCさんは、 建物の外壁を必ず道路から3m以上離して建てなければならない という制限を受けることになります。
このルールによって、道路沿いの建物の位置が揃い、統一感のある美しい街並みが形成されます。
ポイント
特定行政庁は 街並みを整えるために壁面線を指定 できる。
壁面線が指定されると、 建物の外壁をそのラインを超えて建てることはできない。
これにより、 統一感のある景観を維持できる。
都市計画区域外での建築制限
ここまでの規制は 都市計画区域や準都市計画区域 に適用されるものですが、 都市計画区域外でも 一定の場合には適用されることがあります(建築基準法68条の9、施行令136条の2の9第1項)。
たとえば、
- 風致地区(景観を守るための地域)
- 自然公園法に基づく地域
- 特定の保全地域
などでは、都市計画区域外であっても 建築制限が適用されることがある ので注意が必要です。
まとめ
第一種・第二種低層住居専用地域等では、外壁後退距離の制限があり、1.5mまたは1m以上離す必要がある。
美しい街並みを形成するために、特定行政庁は「壁面線」を指定でき、建物の位置を制限できる。
都市計画区域外でも、特定の条件下では建築制限が適用されることがある。
これらの規制はすべて 住環境を整え、安全で快適な街を作るためのもの です。試験対策としても重要ですが、実際に不動産取引や建築に関わるときにも大切なルールとなるので、しっかり理解しておきましょう。