心裡留保のポイント一覧
- 心裡留保(冗談)を相手方が悪意or有過失の場合、契約は無効
- 心裡留保(冗談)を相手方が善意無過失の場合、契約は有効
- 第三者が現れた場合、心裡留保で無効だとしても、冗談を言った者は、善意の第三者には無効を主張できない(善意の第三者に対抗できない)
- 上記第三者は善意であれば対抗でき、無過失でなくてもよい点に注意!
心裡留保の言葉の意味
心理留保とは簡単にいうと、「冗談」で意思表示をすること(契約すること)です。例えば、物の売買でいうと、冗談で「物を売ります」と相手に言うことです。法律用語では、「表意者が真意でないことを知りながら行った意思表示」が心裡留保なのですが、「真意でない」とは、「内心では思っていない」ということです。つまり、内心では思っていないことを、口にして表示しているので、「意思(内心の意思)」と「表示(口にしたこと)」が一致していません。これを「意思の不存在」と言います。
心裡留保の当事者間の関係
この場合、契約は有効なのか?無効となるのか?
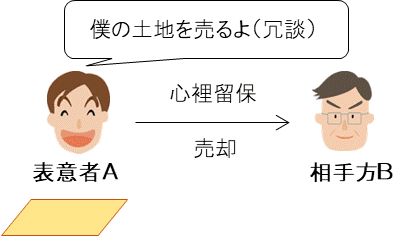
例えば、本人Aがあげるつもりもないのに、「私の土地あげるよ!」
と言ってしまった場合、どうなるか?
まず、冗談で意思表示をした者は、心裡留保の意思表示を表示する者なので「表意者」といいます。つまり、Aが表意者です。一方、Bは、表意者の相手なので「相手方」といいます。
心裡留保の効果
AとBでは、冗談を言ったAが悪いです。しかし、冗談であることを相手方Bが知っていた李(悪意)、または、注意すればわかったという不注意があった(有過失)の場合、相手方Bを守る(保護する)必要はないです。よって、相手方Bが「悪意又は有過失」の場合、心裡留保の意思表示は無効となります。
逆に、相手方Bが、本人が冗談で言っていることを知らず(善意)、さらに、知ることができなかった(無過失)場合は、相手方Bを守ってあゲル必要が高いので、契約を有効としています。つまり、本人が冗談で言っていることを知らず、さらに、知ることができなかった場合、冗談で言ったAの土地は相手方Bのものになってしまうということです。
覚えるべき部分は、「相手方が善意無過失の場合にのみ、契約は有効となり、無効にならない」「それ以外の場合は、契約自体を無効となる」という2つです。
民法93条1項
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
| 心裡留保 | 相手方が悪意または有過失 | 無効 |
|---|---|---|
| 相手方が善意無過失 | 有効 |
すきま時間を使って、基本事項を勉強したい方は、「無料の1日3問まるわかり講座」をご利用していただくのも一つです!
毎日5分の勉強で、着実に実力を上げていただけます!
心裡留保と第三者の関係
本人Aが冗談で相手方Bに「土地をあげるよ」と意思表示をして、相手方Bが第三者Cにその土地を売却した場合どうなるかをお話します。
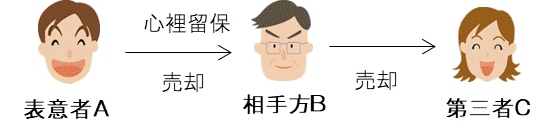
本人Aと相手方Bを「当事者」というのですが、当事者間の契約が有効の場合、第三者Cに売却すれば、もちろん、その土地は第三者Cのものになります。
重要なのは当事者間の契約が無効の場合、つまり、相手方Bが悪意または有過失の場合です。
当事者間の契約が無効なのにもかかわらず、相手方Bが第三者Cに売却した場合
第三者Cが善意の場合、第三者Cへの売却が有効となり、本人Aは無効の主張はできません。
つまり、本人Aを保護するのではなく、第三者Cを保護するとされています。
これを、民法では本人Aは第三者Cに対抗できない(Cから取り戻すことができない)といいます。

心裡留保の問題一覧
■問1
AはBに対してA所有の甲土地を「2000万円で売却する」という意思表示を行ったが当該意思表示はAの真意ではなかった。 Bは真意ではないことについて、知っている場合、当該甲土地を購入する意思表示をすれば、契約は有効となる。 (2007-問1の類題)
答え:誤り
心裡留保の場合、相手方が悪意もしくは有過失の場合、、意思表示は無効となります。 したがって、相手方Bは真意でないことを知っている=悪意なので、当該AB間の契約は無効です。
もし、宅建の勉強をしていて、分からない部分が多いようでしたら、毎日3問・無料のまるわかり講座があるので、ぜひ、ご活用ください!
■問2
AはBに対してA所有の甲土地を「2000万円で売却する」という意思表示を行ったが当該意思表示はAの真意ではなかった。 Bは真意ではないことについて、知らなかったが過失があった場合、当該甲土地を購入する意思表示をすれば、契約は有効となる。 (2007-問1の類題)
答え:誤り
心裡留保の場合、相手方が表意者の真意を知らなかった(善意)としても、過失があれば、無効となります。 したがって、相手方Bは有過失なので、当該AB間の契約は無効です。
■問3
AはBに対してA所有の甲土地を「2000万円で売却する」という意思表示を行ったが当該意思表示はAの真意ではなかった。 Bは真意ではないことについて、知らなかったが重大な過失がない場合、当該甲土地を購入する意思表示をすれば、契約は有効となる。 (2007-問1の類題)
答え:誤り
心裡留保の場合、相手方が表意者の真意を知らなかった(善意)としても、過失があれば、無効となります。 つまり、重大な過失がなくても、軽微な過失があるだけで、無効です。
■問4
AはBに対してA所有の甲土地を「2000万円で売却する」という意思表示を行ったが当該意思表示はAの真意ではなかった。 Bは真意ではないことについて、善意無過失の場合、当該甲土地を購入する意思表示をすれば、契約は有効となる。 (2007-問1の類題)
答え:正しい
心裡留保の場合、相手方が表意者の真意について、知らず(善意)、かつ知らなかったことに過失がない(無過失)場合、真意ではなかったとしても、その意思表示は有効となります。 つまり、AB間の売買契約は有効となります。
■問4
AはBに対してA所有の甲地を売却したが、これはAの真意ではなかった。 その後、Bが、甲地をCに売却し、Cが当該Aの心裡留保について知らなかった場合、CはAに対して甲地の所有権を主張できる。
答え:正しい
心裡留保による無効は善意の第三者に対抗することができません。 今回、第三者Cは心裡留保について知らないので(=善意なので)、CはAに甲地の所有権を主張できます。 逆をいえば、AはCに所有権を主張できません。
■問5
AはBに対してA所有の甲地を売却したが、これはAの真意ではなかった。 その後、Bが、甲地をCに売却した場合、Cが当該Aの心裡留保について善意無過失の場合に限り、CはAに対して甲地の所有権を主張できる。
答え:誤り
心裡留保による無効は善意の第三者に対抗することができません。 したがって、第三者Cは善意でありさえすれば、Aに対抗できます。 つまり、善意「無」過失でなくても、善意「有」過失であれば、CはAに対して甲地の所有権を主張できます。 本問は「善意無過失の場合に限り」という記述が誤りです。
■問6
AはBに対してA所有の甲地を売却したが、これはAの真意ではなかった。 その後、Bが、甲地をCに売却し、Cが当該Aの心裡留保について知らなかったが過失があった場合、AはCに対抗できる。
答え:誤り
心裡留保による無効は善意の第三者に対抗することができません。 本問をみると、Cは知らなかった=善意です。 つまり、Cは善意の第三者です。 したがって、Cが甲地の所有権を主張できるため、AはCに対抗できません(=AはCに所有権を主張できない)。





