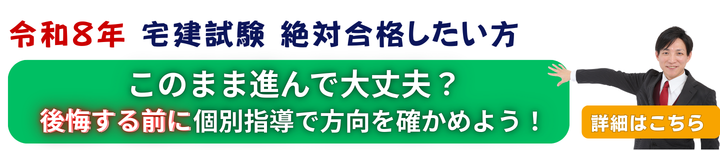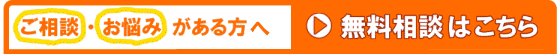(このページは、改正民法に対応しています)
契約解除のポイント一覧
- 契約解除をするためには、原則、催告解除。例外として、一定の場合のみ無催告解除ができる
- 契約が解除されると、原状回復義務が発生する
- 契約が解除されたときに第三者がいた場合、第三者は登記をしていれば、第三者が善意であろうと、悪意であろうと関係なく、第三者が保護される
- 解除権は「全員から全員へ」行うこと(解除権の不可分性)
契約解除の仕方
契約解除をする場合、原則、相当期間を定めて催告し、その期間を過ぎても履行がないとき、契約解除ができます。(=催告解除)
ただし、例外として、下記の場合は催告なく直ちに契約解除ができます。(=無催告解除)
- 履行不能の場合
- 債務者が債務の全部の履行を拒絶している場合
- 「債務の一部が履行不能」または「債務者が債務の 一部を履行拒絶すること」によって残存する部分の みでは契約の目的を達成できない場合
- 特定の日時・一定期間内に債務を履行をしないと 目的を達成できない場合に、その時期が過ぎた場合
上記の細かい具体例については個別指導で解説します!
契約解除されると、その契約は初めからなかったものとされます。
そして、この解除は、解除権をもっているものが、相手に対して、一方的に「解除します!」という意思表示だけで成立し、相手方の承諾は不要です。
原状回復義務
そして、契約が解除されると、当事者双方は、原状回復義務を負います。
例えば、下の例を見てください。AはBから家を購入して代金を支払ったのですが、建物が傾いて、住むことができないことを理由に「契約解除」を申し出ました。契約解除は申し出るだけで解除されるのですが、本人Aは建物を返す義務を負っているし、Bはお金を返す義務を負っています。そして、これは同時履行の関係に立ちます。重要なのは、お金を返す際、代金を受け取った時からの利息を付けて返さないといけない部分です。
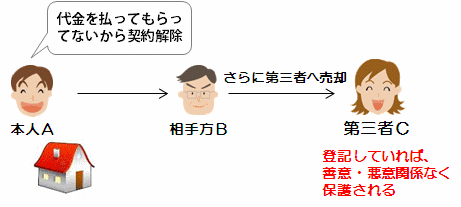
さらに、契約解除をしても、損害が生じている時は、損害賠償請求も併せてできます。
転売されていた場合
下図で、AがBに家を売却し、Bが第三者Cに売却した。しかし、Aは、Bが代金を払ってくれないことを理由に、契約解除をした。この場合、家は誰のものになるか?

この場合、第三者は登記をしていれば、第三者が善意であろうと、悪意であろうと関係なく、第三者が保護されます、つまり、家は第三者の物となります。
この点について、詐欺取消しの場合との違いに注意してください。
取消しの場合は、取消し前の第三者と取消し後の第三者とで扱いがことなります。
取消しの理由は詐欺を例に取っていますが、取消しの場合の考え方は同じです!
解除権の不可分性
当事者の一方が複数人いる場合、契約の解除は原則、その全員から、もしくは、その全員に対して行わなければなりません。
そして、当事者の中の誰かの解除権が消滅した時は、他の者についても消滅します。
解除権は「全員から全員へ」行うことが原則と覚えてください。
ここで、共有物の賃貸借契約解除は管理行為とみなし、共有者の持分の過半数で可能となっていて、解除権の不可分性と矛盾します。
この点について、判例では、共有物の賃貸借契約解除は管理行為とみなし、共有者の持分の過半数で可能としています。
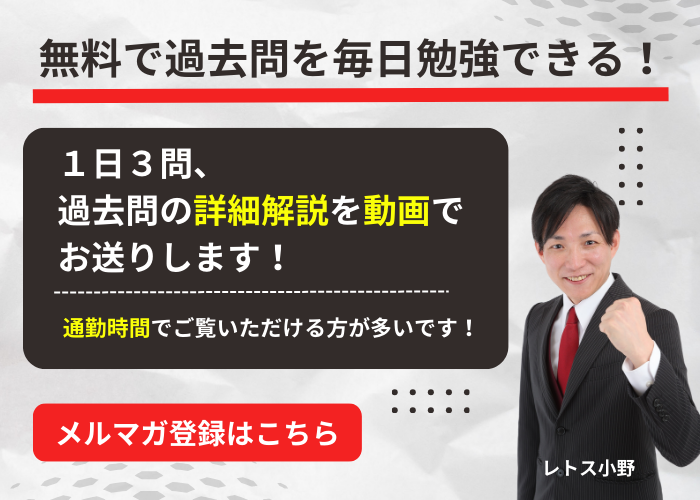
契約解除の問題一覧
■問1
賃借人の債務不履行を理由に、賃貸人が不動産の賃貸者契約を解除するには、信頼関係が破壊されていなければならない旨は民法の条文に規定されている。 (2014-問1-1)
答え:誤り
下記解説は一般的な解説です。
つまり、細かい知識を知らないと解けない解き方です。
もちろん本問は、判例であることを知っている人は多いでしょう。
でも本試験では、判例かどうかも分からないような問題も出題されます。
その時どうしますか?
それでも、答えを見るけるテクニックがあります!
この点は合格するための重要なノウハウなので、「個別指導」で解説しています!
楽に無駄なく短期間で合格したい方は「個別指導」を使って学習することをおススメします!
債務不履行による契約解除についての条文は下記があります。
「当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。」(民法541条)
また、別のルールに下記があります。
「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。そして、賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。」(民法612条)
しかし、本問のような「信頼関係が破壊されていなければならない旨」のルールは規定されていません。
ちなみに、「信頼関係が破壊されて契約解除」というのは、貸主に無断転貸(無断で又貸し)した場合の判例を思い浮かべてください!
これとヒッカケています!転貸や賃借権の無断譲渡が背信的行為と認めるに足りない事情がある場合は、612条による解除はできないと判例では言っています。
※ 背信的行為=信頼関係を破壊する行為(裏切り行為)
612条と判例をまとめると、
原則:無断転貸すると解除できる
例外:信頼関係を破壊するとまではいえない場合は、 解除できない
上記例は民法の条文には規定されていない判例です!
■問2
売主Aは、買主Bとの間で甲土地の売買契約を締結し、代金の3分の2の支払と引換えに所有権移転登記手続と引渡しを行った。その後、Bが残代金を支払わないので、Aは適法に甲土地の売買契約を解除した。Aは、Bが契約解除後遅滞なく原状回復義務を履行すれば、契約締結後原状回復義務履行時までの間に甲土地の価格が下落して損害を被った場合でも、Bに対して損害賠償を請求することはできない。 (2009-問8-4)
答え:誤り
結論から言えば、契約解除と損害賠償請求は同時に行えます!
本問の場合、契約してから原状回復の履行時までの間に甲土地の価格が下落することで売主は損害を被っています。契約解除したからといって併せて損害賠償請求ができないというルールはないので、売主Aは買主Bに対して債務不履行(賃料不払い)に基づく損害賠償請求も行えます。
■問3
売主Aは、買主Bとの間で甲土地の売買契約を締結し、代金の3分の2の支払と引換えに所有権移転登記手続と引渡しを行った。その後、Bが残代金を支払わないので、Aは適法に甲土地の売買契約を解除した。Bは、自らの債務不履行で解除されたので、Bの原状回復義務を先に履行しなければならず、Aの受領済み代金返還義務との同時履行の抗弁権を主張することはできない。 (2009-問8-3)
答え:誤り
契約が解除された場合の売主の「原状回復義務」と買主の「原状回復義務」は同時履行の関係にあります。
つまり、契約解除されることで、売主は「受領した代金+利息」を返還する義務を負い、買主は、「甲土地および甲土地を利用した利益部分(例えば土地の利用料)」を返還する義務を負います。この両者の債務は同時履行の関係にあります。したがって、「Bの原状回復義務を先に履行しなければならず」という記述は誤りです。
「個別指導」では、他分野に渡った関連ポイントについても記載しています。
効率よくつなげて学習を進めていきましょう!
■問4
売主Aは、買主Bとの間で甲土地の売買契約を締結し、代金の3分の2の支払と引換えに所有権移転登記手続と引渡しを行った。その後、Bが残代金を支払わないので、Aは適法に甲土地の売買契約を解除した。Bは、甲土地を現状有姿の状態でAに返還し、かつ、移転登記を抹消すれば、引渡しを受けていた間に甲土地を貸駐車場として収益を上げていたときでも、Aに対してその利益を償還すべき義務はない。 (2009-問8-2)
答え:誤り
契約解除が行われると、両者は原状回復義務を負います。
つまり、本問の場合、売主は、受領した代金に利息をつけて返還し、買主は甲土地と甲土地から得た利益(貸駐車場として収益)を返還しなければなりません。
したがって、本問は正しいです。
本問は問題文の状況を理解するとともに、関連ポイントも一緒に学習しておくと効果的です。
そのため、「個別指導」ではその点も合わせて解説しています。
■問5
所有権がAからBに移転している旨が登記されている甲土地の売買契約に関して、EはBとの間で売買契約を締結したが、BE間の売買契約締結の前にAがBの債務不履行を理由にAB間の売買契約を解除していた場合、Aが解除した旨の登記をしたか否かにかかわらず、Aは所有者であることをEに対して主張できる。 (2008-問2-3)
答え:誤り
「BE間の売買契約締結の前にAがBの債務不履行を理由にAB間の売買契約を解除していた」という記述から、「AB間の契約解除」の後に「BE間の売買契約」があるからEは「解除後の第三者」です。
解除後の第三者とAとの関係は、Bを起点として二重譲渡の関係になり、登記を備えたほうが所有権を対抗できます。
したがって、「Aが解除した旨の登記をしたか否かにかかわらず、Aは所有者であることをEに対して主張できる」という記述は誤りです。AがEに所有者であることを主張するには、Aは解除した旨の登記が必要です。
解除と第三者との関係は簡単に考えてもよいでしょう!その点は「個別指導」でお伝えします!
■問6
不動産売買契約に基づく所有権移転登記がなされた後に、売主が当該契約を適法に解除した場合、売主は、その旨の登記をしなければ、当該契約の解除後に当該不動産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。 (2007-問6-2)
答え:正しい
解除の場合、解除前に第三者が現れても、解除後に第三者が現れても先に登記を備えたほうが勝ちます。
解除についてはこのルールだけ覚えておきましょう。
つまり、売主が第三者に所有権を対抗するためには、先に「解除による所有権の登記」を備えておく必要があります。
したがって、「売主は、その旨の登記をしなければ、解除後に当該不動産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。」という記述は正しいです。
■問7
買主が、売主に対して手付金を支払っていた場合には、売主は、自らが売買契約の履行に着手するまでは、買主が履行に着手していても、手付金の倍額を買主に支払うことによって、売買契約を解除することができる。 (2005-問9-4)
答え:誤り
買主が履行に着手している場合、手付金の倍額を返しても、売主は契約解除をすることができません。
本問は「買主が履行に着手していても」という記述から買主は履行に着手していることを前提に考えます。
したがって、履行に着手している買主の相手方(売主)は手付の倍額を返しても(償還しても)契約解除はできません。
本問は「解約手付」の内容です。「個別指導」の解説でしっかり理解しておきましょう!
解約手付は民法だけでなく、宅建業法の8種制限でも出てきますので!
■問8
宅地建物取引業者であるAが、自らが所有している甲土地を宅地建物取引業者でないBに売却した場合、甲土地に設定されている抵当権が実行されてBが所有権を失った場合、Bが甲土地に抵当権が設定されていることを知っていたとしても、BはAB間の売買契約を解除することができる。 (2008-問9-2)
答え:正しい
本問は「売主の担保責任」の問題ですが、この分野でも「契約解除」は出てきます!
契約解除は広い分野で関連してくる部分なので、一緒に勉強しておきましょう!
抵当権のついた物件の売買をし、その後、抵当権の実行により所有権を失った場合、抵当権が付着していることについて買主の善意・悪意関係なく、契約解除ができます。したがって、本問は買主が悪意ですが、解除できます。
この点について関連ポイントもあるのでその点も学習しておきましょう!
「個別指導」では関連ポイントもまとめて解説しています。
■問9(改正民法)
Aを売主、Bを買主とする甲土地の売買契約が締結された。 Bが、A所有の甲土地が抵当権の目的となっていることを知りながら本件契約を締結した場合、当該抵当権の実行によってBが甲土地の所有権を失ったときは、Bは、本件契約を解除することができる。(当該抵当権は契約内容に適合しないものとする) (2016-問6-4)
答え:正しい
AがBに売却した土地に抵当権が設定されていたので、抵当権付着物売買です。
A→B
契約内容に適合しない抵当権が付着していた場合、当該抵当権が実行され、所有権を失ったとき、買主Bが善意でも悪意でも「損害賠償請求」も「契約解除」もできます。
したがって、「抵当権の実行によって買主Bが甲土地の所有権を失なったときは、
買主Bは、AB間の売買契約を解除することができる。」という記述は正しいです。
■問10
宅地建物取引業者でも事業者でもないAB間の不動産売買契約において、買主Bが不動産に瑕疵があることを契約時に知っていた場合や、Bの過失により不動産に瑕疵があることに気付かず引渡しを受けてから瑕疵があることを知った場合には、Aは瑕疵担保責任を負わない。 (2007-問11-3)