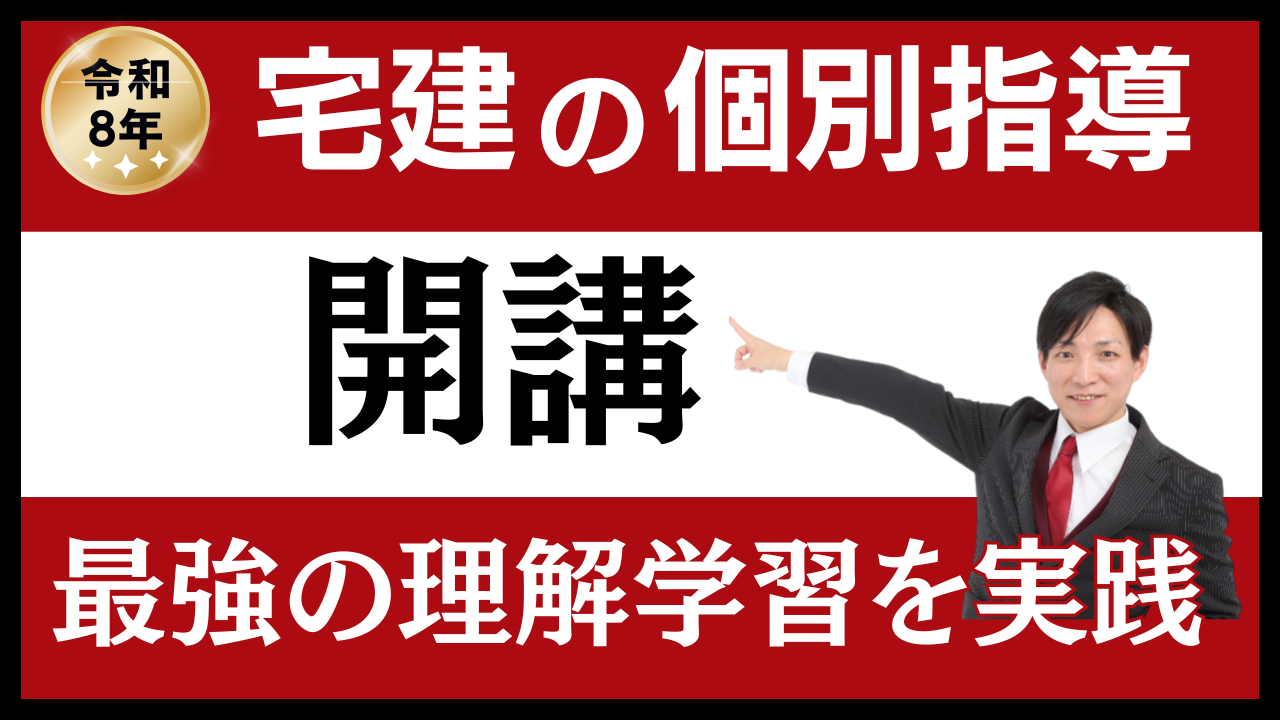宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問におい「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1.宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地又は建物の取引に関する実務の経験期間が2年に満たない場合であっても、試験に合格した日から1年以内に登録を受けようとするときには、都道府県知事が指定する講習を受講することにより、宅地建物取引士の登録を受けることができる。
2.宅地建物取引士証は、更新を受けることなくその有効期間が経過した場合、その効力を失うが、当該宅地建物取引士証を都道府県知事に返納する必要はない。
3.宅地建物取引士は、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義で宅地建物取引士である旨の表示をしたときは、法第68条の規定に基づく処分の対象となるが、当該他人が宅地建物取引士の登録を受けた者であるときはこの限りでない。
4.宅地建物取引業者は、その事務所唯一の専任の宅地建物取引士が宅地建物取引士証の有効期間の経過により効力を失い宅地建物取引士でなくなったときは、2週間以内に法第31条の3第1項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
1・・・ 誤り
宅建士の登録を受けるには、2年以上の実務経験が必要です。ただし、実務経験が足りない場合でも、登録実務講習を修了すれば登録できます。
本肢は、「都道府県知事が指定する講習(法定講習)」を受ければ登録できると書かれていますが、これは誤りです。
宅建士の登録に必要なのは、「国土交通大臣が登録した講習(登録実務講習)」です。
【法定講習との違い】
都道府県知事が指定する講習」は法定講習と呼ばれ、登録後に宅建士証を交付する前に受けるものです。
一方、「登録実務講習」は、実務経験が足りない人が登録資格を得るために受けるものです。
そして、宅建士試験合格から1年以内であれば、法定講習は免除されます。しかし、登録要件(実務経験または登録実務講習修了)は必要です。
よって、本肢のように、「都道府県知事が指定する講習」で登録できるとするのは誤りです。登録するためには、「登録実務講習」の修了が必要です。
2・・・ 誤り
宅地建物取引士証は、有効期間が切れて使えなくなった場合や、登録が抹消された場合には、すぐに(速やかに)交付を受けた都道府県知事に返さなければなりません(宅建業法22条6項)。
つまり、期限切れや登録抹消で取引士証が無効になったときに、返さなくてもよいわけではなく、必ず返納が必要という決まりになっています。
3・・・ 誤り
宅地建物取引士が 他人に自分の名義を貸すこと(名義貸し) は法律違反です。そして、その名義を借りた人が「宅地建物取引士である」と表示した場合には、宅建業法第68条に基づいて処分の対象になります。
重要なのは、名義を借りた人が宅地建物取引士の資格を持っている場合でも、名義貸しをした側は処分を免れない という点です。たとえ相手が資格を持っていても、正式な手続きを経ずに名義を使わせる行為自体が禁止されています。よって、本肢は「当該他人が宅地建物取引士の登録を受けた者であるときはこの限りでない。」という記述が誤りです。
宅地建物取引士は、自分の名義を他人に使わせないよう十分注意する必要があり、違反した場合は、都道府県知事から指示を受けたり、さらに重い処分が下される可能性があります。
問題文の理解が重要なので、問題文の理解の仕方は個別指導で解説します。
4・・・ 正しい
宅建業法では、事務所には 宅地建物取引士(宅建士) を専任で配置するルールがあります。具体的には、事務所にいる従業員5人ごとに1人以上の宅建士を専任で置く必要があると決められています。
今回のケースでは、事務所に配置されていた唯一の専任宅建士が資格を失ってしまいました。この状態では、宅建業法のルールを満たしていない違反状態になってしまいます。
そのため、宅建業者は違反状態を早急に改善しなければなりません。法律では、2週間以内に新しい宅建士を専任で配置するなど必要な対応をとることが求められています(宅建業法31条の3第3項)。
よって、本肢は正しいです。
令和6年(2024年):宅建試験・過去問
- 問1
- 法律関係
- 問2
- 委任契約
- 問3
- 共有
- 問4
- 民法総合
- 問5
- 履行遅滞
- 問6
- 地上権
- 問7
- 賃貸借
- 問8
- 民法の条文
- 問9
- 承諾・債務引受
- 問10
- 契約不適合責任
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 盛土規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 住宅ローン控除
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価基準
- 問26
- 35条書面
- 問27
- 宅建業法総合
- 問28
- 報酬計算
- 問29
- 宅建士
- 問30
- クーリングオフ
- 問31
- 宅建業法総合
- 問32
- 媒介契約
- 問33
- 広告
- 問34
- 手付金等の保全措置
- 問35
- 37条書面
- 問36
- 営業保証金
- 問37
- 35条書面
- 問38
- 免許
- 問39
- 案内所
- 問40
- 37条書面
- 問41
- 重要事項説明
- 問42
- 死に関する告知
- 問43
- 宅建士証
- 問44
- 37条書面
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物