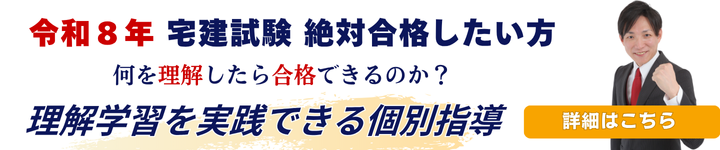盛土規制法とは
盛土規制法(正式名称:「宅地造成及び特定盛土等規制法」)は、宅地造成や特定の盛土、または土石の堆積によって生じる崖崩れや土砂流出による災害を防止するために制定された法律です(第1条)。
日本では地震や豪雨による土砂災害が多発しており、とくに宅地造成地や盛土が行われた土地では、適切な規制が行われなければ災害の危険性が高まります。そのため、この法律では、特定の区域を指定して宅地造成等に関する工事を規制し、必要な安全対策を講じることを義務付けています。
盛土規制法の適用範囲
盛土規制法では、災害防止の観点から以下の区域を指定し、それぞれに応じた規制を設けています。
(1) 宅地造成等工事規制区域(第10条)
都道府県知事は、基礎調査の結果を踏まえ、関係市町村長(特別区の長を含む)の意見を聴いたうえで、宅地造成や特定盛土等に伴う災害が発生する恐れが大きい土地を 「宅地造成等工事規制区域」 として指定することができます。
この区域に指定されると、以下のような規制が課されます。
- 宅地造成等の工事を行うには都道府県知事の許可が必要(第12条)
- 許可を受けずに工事を行うことは禁止
- 宅地造成後の保全義務が発生(第22条)
具体例
急傾斜地を造成して住宅地にしようとする場合
→ この区域に指定されていると、工事前に都道府県知事の許可を得なければならない。
(2) 造成宅地防災区域
造成された宅地の安全性が十分に確保されていない場合、都道府県知事が 「造成宅地防災区域」 を指定し、改善命令などを発出することができます。
具体例
過去の盛土造成地で地盤が緩んでいると判明した場合
→ 都道府県知事が区域を指定し、所有者に対して擁壁の設置などを求めることができる。
(3) 特定盛土等規制区域
特に大規模な盛土などを行う場合、崩壊のリスクが高くなるため、都道府県知事は 「特定盛土等規制区域」 を指定し、工事の安全対策を厳しく規制することができます。
宅地造成等工事規制区域内の規制
許可制(第12条)
宅地造成等工事規制区域内で宅地造成等の工事を行う場合、工事主は、工事に着手する前(事前に)都道府県知事の許可を得る必要があります。
ただし、都市計画法による開発許可を受けた場合 には、宅地造成等工事規制区域における許可を受けたものとみなされます(第15条)。つまり、宅地造成等の許可は不要です。
工事計画の変更時の対応(第16条)
一度許可を得た工事であっても、その後に計画変更が生じた場合は、原則として再度都道府県知事の許可を受ける必要があります(第16条第1項)。
これは、変更が安全性や周辺環境に影響を及ぼす可能性があるためです。
しかし、以下のような 「軽微な変更」 については、許可は不要であり、「遅滞なく届け出る」ことで足ります(第16条第2項、規則第38条)。
「工事主」の定義(第2条第7号)
「工事主」とは、以下のいずれかに該当する者を指します。
- 工事の注文者(請負契約の発注者)
宅地造成、特定盛土等、または土石の堆積を伴う工事を、工事業者に委託する者。
例:不動産開発業者や土地所有者が、工事会社に造成工事を依頼する場合。 - 請負契約によらず自ら工事を行う者
自社施工をする者も含まれる。
例:建設業者が、自らの土地を宅地に造成する場合。
つまり、単に「発注する側」だけでなく、「自分で工事をする場合」も工事主に該当する点に注意が必要です。
「宅地」の定義(第2条第1号)
「宅地」とは、以下に該当しない土地のことを指します。
【宅地に該当しない土地】
- 農地・採草放牧地・森林(農地等)
農地法で規定される農地や、草を採るための土地、森林。 - 公共施設用地(道路・公園・河川など)
道路や公園、河川など公共のために利用される土地。 - 政令で定める公共の用に供される施設の用地
具体例(施行令第2条):
砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場・航空保安施設、鉄道用地、国または地方公共団体が管理する学校、運動場、墓地など
【宅地に該当する土地】
上記に該当しない 一般的な住宅地、商業地、工業地などの土地 は、原則として「宅地」となります。
「宅地造成」の定義(第2条第2号)
「宅地造成」とは、以下の 2つの条件を同時に満たす工事を指します。
- 宅地以外の土地を宅地にするための工事
目的が 宅地化 であることが前提。
例:山林や農地を住宅地にするために整地する場合。
※ 宅地を宅地以外に変更する工事(例:宅地を森林に戻す)は「宅地造成」には該当しない。 - 一定規模を超える「土地の形質変更」
「土地の形質変更」とは、土地の高さや形状を変えることを指します。
宅地造成に該当するかどうかは 規模の基準 によって決まります(施行令第3条)。
宅地造成の規模の基準(上記一定規模とは)
宅地造成に該当するかどうかを判断するために、以下の規模基準が定められています。
| 種類 | 具体的な基準 |
|---|---|
| 盛土(もりど) | 高さ1mを超える崖を生じるもの |
| 切土(きりど) | 高さ2mを超える崖を生じるもの |
| 盛土 + 切土 | 高さ2mを超える崖を生じるもの |
| 造成面積 | 500㎡を超える場合 |
| 崖を生じない盛土 | 高さ2mを超える場合 |
※盛土(もりど):低い土地に土を積み上げて高くすること。
※切土(きりど):高い土地を削って低くすること。
※「崖を生じる」とは、工事によって 急斜面が発生する ことを意味します。
この崖の高さが基準を超えると 宅地造成に該当し、許可が必要 になります。
宅地造成の許可が必要なケース
上記「宅地造成の規模の基準」から分かるように「宅地造成等工事規制区域(規制区域)」内では、以下の工事を行う場合に 都道府県知事の許可 が必要です。
- 高さ1mを超える崖を生じる盛土
- 高さ2mを超える崖を生じる切土
- 高さ2mを超える崖を生じる盛土と切土
- 造成面積が500㎡を超える場合
- 崖を生じない場合でも、高さ2mを超える盛土
宅地造成の許可が不要なケース
- 宅地を宅地以外にする場合(例:宅地を森林に戻す)
- 崖を生じない 高さ2m以下の盛土
- 造成面積500㎡以下の小規模工事
技術的基準の遵守義務(13条1項)
宅地造成等工事規制区域(規制区域)内で行われる宅地造成等工事は、以下の基準に従い、擁壁や排水施設の設置など災害防止のための必要な措置を講じることが求められます。
- 擁壁の設置
- 排水施設の設置
- その他、宅地造成等に伴う災害を防止するための措置
これらの技術的基準は 政令 によって定められており、基準に適合しない工事は認められません。
一定規模以上の工事における設計者の要件(13条2項、施行令21条)
以下の工事を行う場合、一定の資格を有する者 による設計が必要となります。
- 高さ5mを超える擁壁の設置
- 盛土または切土をする土地の面積が1,500㎡を超え、排水施設を設置する場合
「一定の資格を有する者」とは、通常、建築士や土木施工管理技士 などの専門資格を有する者を指します。無資格者の設計による工事は許可されません。
許可申請と審査(14条1項)
工事を行うには、都道府県知事の許可を受ける必要があります。申請後、都道府県知事は「遅滞なく」許可または不許可の処分 を行う義務があります。
許可のポイント
- 申請された工事計画が 技術的基準 を満たしているか
- 災害防止のための措置が適切か
- 規制区域内の土地利用や周辺環境への影響を考慮しているか
これらの観点から、都道府県知事が慎重に審査を行い、基準を満たさない場合は不許可となります。
許可処分の通知と条件の付与(14条2項、12条3項)
許可または不許可の処分が決定した場合、以下の手続きが行われます。
- 許可された場合 → 許可証の交付
- 不許可の場合 → 文書による通知
また、許可をする際に、工事の実施に伴う災害を防止するため必要な条件を付与できる(12条3項)とされています。例えば、以下のような条件が付されることがあります。
- 追加の排水施設の設置
- 工事の進行管理の強化
- 地盤改良の実施
このように、都道府県知事は災害防止のために適切な措置を要求することができます。
工事完了後の検査(17条1項・2項)
許可を受けた工事を完了した後、工事主は以下の手続きを行わなければなりません。
- 工事完了から4日以内 に完了検査を申請
- 都道府県知事による検査を受ける
- 検査の結果、適合していれば「検査済証」が交付される
この「検査済証」(けんさずみしょう)が交付されることで、工事が適法に完了したことが証明されます。もし技術的基準に適合しない場合は、是正指示が出される可能性があります。
届出制(第21条)
許可が必要な宅地造成等工事に該当しない場合でも、災害に影響を与える一定の行為については都道府県知事への 届出が必要 となります。
| 届出の内容 | 届出期間 |
|---|---|
| すでに工事が行われている土地が指定された場合 | 指定日から21日以内 |
| 規制区域内で2mを超える擁壁等の除去工事をする場合 | 工事開始14日前まで |
| 公共施設用地を宅地または農地に転用する場合 | 転用日から14日以内 |
保全義務・勧告(第22条)
土地の所有者、管理者、占有者は、宅地造成等に伴う災害が発生しないよう 土地を常時安全な状態に維持する義務 があります。
都道府県知事は、その土地の所有者、管理者、占有者、工事主、工事施行者に対して適切な保全措置をとるよう勧告を行うことができます。
具体例
古い盛土造成地で地盤沈下の兆候が見られた場合
→ 都道府県知事が所有者に対して地盤改良や擁壁の補強を勧告する。
改善命令(第23条)
勧告を無視し、放置すると危険が高まる場合、都道府県知事は 「改善命令」 を発出できます。
- 擁壁の設置・改造
- 盛土や地形の改良
- 土石の除却
これらの措置を 期限を設けて命じる ことができます。
具体例
斜面が崩れかかっているが所有者が対応しない場合
→ 都道府県知事が改善命令を出し、必要な工事を命じる。
報告の徴取(第25条)
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者や工事主に対し、土地や工事の状況について報告を求めることができます。
造成宅地防災区域
造成宅地防災区域とは、宅地造成に伴う災害を防ぐために指定される区域です。崖崩れや土砂の流出などのリスクが高い地域を対象に、都道府県知事が指定するものです。これにより、住宅地としての安全性を高めることが目的とされています。
造成宅地防災区域の指定(盛土規制法45条1項)
都道府県知事は、次の条件に当てはまる土地を造成宅地防災区域として指定することができます。
- 宅地造成等工事規制区域ではない土地
- 宅地造成や特定盛土等によって災害の発生が懸念される区域
- 多くの居住者に危険を及ぼす可能性がある区域
- 一定の基準に該当する一団の造成宅地(付随する道路などを含む)
この指定にあたっては、関係する市町村長の意見を聴いた上で判断されます。
具体例
例えば、ある地域に大規模な宅地造成が行われたとします。しかし、その地域はもともと山を削って造成された土地で、強い雨が降ると地盤が緩みやすい場所です。このような場合、都道府県知事はその地域を「造成宅地防災区域」に指定し、適切な対策を義務付けることができます。
造成宅地防災区域内での防災措置(46条・47条)
造成宅地防災区域に指定されると、土地の所有者や管理者は、災害を防ぐために必要な措置を取ることが求められます。
所有者・管理者の努力義務(46条1項)
造成宅地防災区域内の土地の所有者・管理者・占有者は、次のような対策を講じるよう努めなければなりません。
- 擁壁(ようへき) の設置や改修(崩壊を防ぐ壁の設置)
- その他、崖崩れや土砂流出を防ぐための措置
具体例
例えば、宅地のすぐ裏が急な崖になっている場合、所有者は崖崩れを防ぐためにコンクリート擁壁を設置することが推奨されます。
都道府県知事の勧告(46条2項)
都道府県知事は、必要と判断した場合、所有者・管理者または占有者に対して以下の措置を取るよう勧告することができます。
- 擁壁の設置や改修
- そのほか、災害防止のための工事
具体例
ある造成地で、小規模な崖崩れが発生しました。都道府県知事は、今後の大規模な崩落を防ぐために、所有者に対して擁壁の強化工事を行うよう勧告することが
できます。
都道府県知事の命令(47条1項)
さらに、次のような状況にある場合、都道府県知事は所有者・管理者または占有者に対して命令を出すことができます。
- 擁壁などが設置されていない、または不完全である
- そのまま放置すると災害の発生リスクが高い
- 土地の利用状況などを考慮して、対策が相当であると判断される
命令が出された場合、指定された猶予期間内に以下の措置を取る必要があります。
- 擁壁などの設置や改修
- 地形の改良
- 盛土の改善工事
具体例
ある地域で、台風の影響により崖崩れが発生しました。この崖崩れは、擁壁が不十分だったことが原因です。都道府県知事は、これ以上の被害を防ぐため、所有者に対して一定期間内に擁壁を補強するよう命令を出しました。
特定盛土等規制区域
規制区域の指定
特定盛土等規制区域とは、宅地造成等工事規制区域以外の区域で、大雨や地震などの影響で崖崩れや土砂流出が発生する危険性が特に高い地域を指します。都道府県知事が、市町村長の意見を聞いたうえで、土地の傾斜や渓流の位置、周辺の土地利用の状況などを調査し、災害の発生リスクが特に大きいと判断した場合に指定されます(盛土規制法26条1項)。
特定盛土等の定義
「特定盛土等」とは、宅地、農地、採草放牧地、森林において行われる盛土やその他の土地の形質変更のうち、近隣の宅地に災害を引き起こす恐れが大きいものを指します(盛土規制法2条3号)。
具体例
- 山の斜面を削って宅地開発を行う際に、大量の土砂を盛る行為
- 農地を埋め立てて商業施設を建設するための土地改変
土石の堆積
「土石の堆積」とは、宅地、農地、採草放牧地、森林において行われる土石の堆積のうち、一定期間後に除去することを前提とするものを指します(盛土規制法2条4号)。
具体例
- 建設工事で発生した土砂を一時的に積み上げる行為
- 採石場から搬出された石を一時的に貯める行為
届出制について
特定盛土等規制区域内で盛土や土石の堆積を行う場合、工事の開始30日前までに都道府県知事に工事計画を届け出る必要があります(盛土規制法27条1項)。
ただし、政令で定められた「災害の恐れがない工事」は届出が不要です(同法27条1項但書)。
具体例
- 2m以下の小規模な盛土
- 一時的な土砂の積み上げ(短期間で撤去する場合)
また、届出が必要な工事の規模は、宅地造成等工事規制区域における許可制と同じ基準(下表参照)が適用されます(盛土規制法2条2号、3号、施行令3条)。
| 種類 | 具体的な基準 |
|---|---|
| 盛土(もりど) | 高さ1mを超える崖を生じるもの |
| 切土(きりど) | 高さ2mを超える崖を生じるもの |
| 盛土 + 切土 | 高さ2mを超える崖を生じるもの |
| 造成面積 | 500㎡を超える場合 |
| 崖を生じない盛土 | 高さ2mを超える場合 |
特定盛土等規制区域の許可制について
特定盛土等規制区域内で、一定の規模を超える盛土や土石の堆積を行う場合、工事の着手前に都道府県知事の許可を受けなければなりません(盛土規制法30条1項)。
| 盛土・切土の種類 | 許可が必要な基準 |
|---|---|
| 盛土 | 2mを超える崖を生じるもの |
| 切土 | 5mを超える崖を生じるもの |
| 盛土と切土 | 合わせて5mを超える崖を生じるもの |
| 盛土(崖を生じない場合) | 高さ5mを超えるもの |
| 面積 | 3,000㎡を超えるもの |
ただし、政令で定める「災害の恐れがない工事」は許可不要です(同法30条1項但書)。
許可が必要な「土石の堆積」
| 土石の堆積の条件 | 許可が必要な基準 |
|---|---|
| 高さ5m超かつ面積1,500㎡超のもの | 許可必要 |
| 高さ5m以下で面積3,000㎡超のもの | 許可必要 |
具体例
- 住宅地に隣接する山の斜面に5mを超える盛土をする場合
- 1,500㎡以上の土地に高さ5mを超える土砂を積み上げる場合
その他(既存工事の対応)
特定盛土等規制区域に指定された時点で、すでに工事が進行中(着手済)であった場合、その工事主は指定があつた日から21日以内に都道府県知事に届け出る義務があります(盛土規制法40条)。
これは、宅地造成等工事規制区域の届出制度と同様のルールとなっています。
具体例
すでに工事が進んでいる宅地開発が、新たに規制区域に指定された場合、工事を継続するには届出が必要
監督処分等
宅地造成や工事の適正な実施を確保するため、一定のルールが法律で定められています。これに違反した場合、都道府県知事は違反者に対して監督処分を行うことができます。ここでは、監督処分の種類や対象者について、具体例を交えながら詳しく解説していきます。
監督処分の対象となるケース
都道府県知事は、以下のような違反行為に対して、必要な監督処分を行います。
(1)偽りその他不正な手段による許可の取得・許可条件違反
具体例
ある業者が宅地造成の許可を得るために、実際には存在しない施工計画を申請書に記載し、虚偽の許可を得た場合。このような場合、都道府県知事はその許可を取り消すことができます(宅地造成等規制法20条1項)。また、許可を得た後に定められた条件に違反した場合も同様に、許可の取消し対象となります。
(2)工事の基準に不適合な施工・中間検査申請なし
具体例
宅地造成工事の中間検査を受けずに、擁壁の設置を不適切に行い、法的基準に合わない状態で工事を進めた場合。この場合、都道府県知事は工事主や請負人に対して工事の施行の停止を命じることができます。また、中間検査を受けるべき段階で適切な申請を行わなかった場合も、監督処分の対象となります。
(3)完了検査未実施または基準不適合
具体例
宅地造成工事が完了したにもかかわらず、完了検査を受けずに販売を開始した業者がいた場合、この業者は監督処分の対象となります。さらに、完了検査を受けたが、その結果が基準を満たしていなかった場合も、改善命令が出される可能性があります。
(4)堆積土石の除却確認申請なし・不十分な除却
具体例
山を切り開いて宅地造成を行った際に、大量の土石が堆積した状態のまま放置し、除却の確認申請を行わなかった場合。土砂崩れの危険があるため、都道府県知事は土地の所有者や管理者に対して適切な除却を命じることができます。また、申請を行ったものの、実際には除却が不完全だった場合も処分の対象となります。
(5)災害防止のための措置が必要な場合
具体例
ある宅地が土砂崩れの危険区域に位置しており、適切な擁壁が設置されていない場合。都道府県知事は、土地の所有者や管理者に対して擁壁の設置や地盤の補強を求めることができます。さらに、災害発生の恐れが特に大きい場合には、工事の施行の停止や土地の使用制限を命じることも可能です。
| 監督処分の種類 | 適用対象 |
|---|---|
| 工事の施行の停止 | 工事主、工事の請負人、現場管理者 |
| 擁壁等の設置その他災害防止のための措置 | 所有者、管理者、占有者、工事主、工事施行者 |
| 土地の使用の禁止 | 所有者、管理者、占有者、工事主 |
| 土地の使用の制限 | 所有者、管理者、占有者、工事主 |
| 報告の徴取(工事の状況確認) | 所有者、管理者、占有者 |
| 改善命令(擁壁の設置、盛土の改良など) | 所有者、管理者、占有者 |