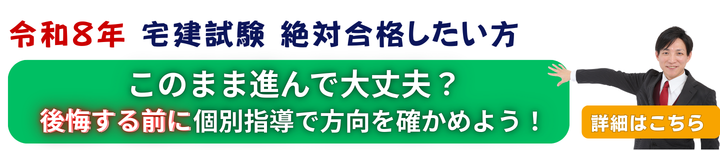宅地取引において、土地取引を自由に行える「届出制」と異なり、都道府県知事の許可を必要とする厳しい規制が「許可制」です。許可制が適用されると、規制区域内では取引する土地の規模にかかわらず、必ず都道府県知事の許可を受けなければなりません。
しかし、許可制は個人の財産権や経済活動への大きな制約となるため、これまで実際に規制区域が指定されたことはありません。
規制区域とは
許可制が適用される「規制区域」とは、以下の条件に該当する地域を指します。
都市計画区域内
- 土地の投機的取引(転売目的の売買)が広範囲に集中して行われ、またはそのおそれがある。
- 地価が急激に上昇している、またはそのおそれがある。
都市計画区域外
上記のような事態が発生するおそれがあり、早急に対処しないと適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となると認められる区域。
具体例
例えば、ある地域で大規模な商業施設の開発計画が発表された場合、土地の価格が急激に上がり、不動産業者や投資家が転売目的で土地を買い占める可能性があります。このような状況を防ぐために規制区域の指定が検討されることがあります。
許可制の適用範囲
規制区域に指定された場合、その区域内で行われる土地取引には、土地の面積に関係なく都道府県知事の許可が必要となります。
また、許可を得ないで取引を行った場合、その契約は無効となります。
具体例
規制区域内のAさんが、自分の所有する100平方メートルの土地をBさんに売却しようとした場合、面積が小さくても許可が必要です。もし許可を得ずに契約を締結してしまうと、その契約は無効となります。
不服申立て
土地取引の許可が下りなかった場合、申請者は以下の対応をとることができます。
- 土地利用審査会に審査請求を行う。
- 都道府県知事に土地の買取請求を行う。
具体例
Cさんが規制区域内の土地を購入しようとしたが、不許可となった場合、都道府県に対して不服を申し立てることができます。また、Cさんが「この土地を売ることができないなら、行政に買い取ってほしい」と請求することも可能です。
遊休土地に関する措置
「遊休土地」とは、届出や許可の手続きを経て取得されたものの、長期間利用されず放置されている土地を指します。
遊休土地の問題点
遊休土地が増えると、次のような問題が発生します。
- 土地不足の発生 → 使える土地が減ることで、土地価格の上昇を招く。
- 意図的な地価のつり上げ → 値上がりを狙って土地を放置する投機行為。
特に、届出・許可を受けて取得した土地は、利用目的を明確にして取得されているため、そのまま放置されることは望ましくありません。
遊休土地への対応策
都道府県知事は、遊休土地について以下の措置を講じることができます。
- 遊休土地通知
都道府県知事は、土地所有者に対して「遊休土地である」という通知を行い、利用・処分の計画を提出するよう求める。(国土利用計画法28条、29条) - 助言・勧告
計画が適切でない場合は、適正な利用に向けた助言や勧告を行う。(国土利用計画法30条、31条) - 買取り協議
勧告に従わない場合、地方公共団体などがその土地の買取りを希望する場合、買取り協議が行われる。(国土利用計画法32条)
Dさんが、都市開発目的で購入した土地を10年間放置していた場合、都道府県知事から「遊休土地である」と通知を受けることになります。その後、適正な利用計画を提出するよう求められ、対応しなければ勧告を受ける可能性があります。