分筆登記と合筆登記のポイント一覧
| 合筆が禁止されている場合 |
|---|
| 相互に接続していない土地(隣地でない土地) |
| 所有者・地目・地番区域を異にする土地 |
| 「所有権の登記」以外の「権利」がある土地 →合筆する一方の土地に抵当権が付着している →例外)要役地の地役権の付着した土地は合筆できます |
| 所有権の登記のある土地と所有権の登記のない土地 →誰のものか確定していないから土地を合筆できない |
分筆登記とは?
宅地などの土地の数え方の単位は「筆(ふで、ひつ)」です。
一筆の土地を複数の筆に分けることを分筆と言います。
それゆえ、分筆前の地積(土地の面積)と分筆後の地積の合計は同じでなければなりません。
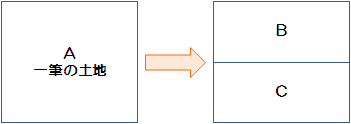
では誰が分筆するのでしょうか?
分筆登記の申請人
- 所有権の登記がない不動産の表題部所有者
- 所有権の登記名義人
登記がない所有者も分筆登記できるようにしたのは、もし「所有権の登記名義人」しか分筆できないとすれば所有権保存登記をしていない土地の所有者が分筆できなくなってしまうからです。
次に、分筆する土地に抵当権や地役権などが付着していた場合、登記で必要な書類が試験で問われてきます。
担保権(抵当権、質権、先取特権)のある土地の分筆
共同担保目録を添付しなければならない。
共同担保目録とは
同一債権の担保として、複数の不動産の上に設定された抵当権を設定するための書類のこと。今回、分筆することで、分割後の数筆の土地が同一の債権を担保することになります。
地役権のある土地の分筆
地役権証明情報を添付しなければならない。
地役権証明情報とは
・地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報
・地役権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
を言い、なぜ必要かというと、登記申請に地役権者が含まれていないので、地役権の存続などについて地役権者の意思確認を図るためです。
合筆登記
複数の土地を一筆の土地にまとめることを合筆と言います。
合筆で試験に問われるのは「合筆できないのはどのような場合か」という点です。
| 合筆が禁止されている場合 |
|---|
| 相互に接続していない土地(隣地でない土地) |
| 所有者・地目・地番区域を異にする土地 |
| 「所有権の登記」以外の「権利」がある土地 →合筆する一方の土地に抵当権が付着している →例外)要役地の地役権の付着した土地は合筆できます |
| 所有権の登記のある土地と所有権の登記のない土地 →誰のものか確定していないから土地を合筆できない |







