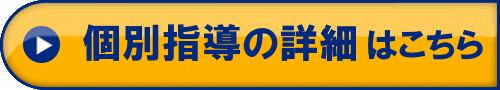おはようございます!レトスの小野です!
- 理解学習を実践できていない
- 計画を立てられていない
- 計画は立てたけど勉強が続けられていない
- 勉強の仕方が分からない
- 模試では点数が取れていたのに、本試験では点数が取れない
これらの課題は解決しないと来年の合格は厳しいです。
また、大手の予備校や通信講座を受講しても、これらの課題は解決してくれません。
解説するのはあなた自身で考え、行動する必要があります!
もし、自分で解決するのは難しいというのであれば是非、個別指導をご検討ください!
これまで、多くの受講者を合格に導いてきましたが、もともと上記のような課題を持った方ばかりです。
私には、解決策があります!
一緒に勉強して来年絶対合格しましょう!

【問1】不法行為
人の生命または身体の侵害による不法行為の被害者は、損害賠償債権を自働債権として、
加害者に対する金銭返還債務と相殺することができる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
人の生命または身体の侵害による被害者に対してきちんと弁済させることから、
人の生命や身体の侵害による不法行為(例えば、人身事故)の加害者側からは相殺できません。
それに対して、被害者側からは相殺することができます。
言い換えると、
損害賠償請求権を自働債権として相殺することはできますが、
損害賠償債務を受働債権として相殺することはできない
ということです!
このあたりは、どっちがどっちだったっけ?
と悩む方がいますが、
「被害者を保護するための規定」であることと
「自働債権と受働債権」の言葉の意味
を知っていれば解けます!
つまり、簡単ということです!
こんなところでつまずいていてはいけませんよ!
参考ページはこちら>>
個別指導の受講者様には、他の関連ポイントを含めて解説します!
理解すべき問題なので絶対理解してください!
理解できれば簡単な問題です!
【問2】宅建士
宅地建物取引士資格試験に合格した日から1年以内であれば、
登録をしている都道府県知事が指定する講習を受講しなくても、
取引士証の交付を受けることができる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
取引士証の交付を申請するには、
原則、登録している知事が指定する講習
(交付申請前6月以内に行われるもの)
を受講する必要があります。
ただし、
「宅建試験に合格して1年以内に交付申請する場合」や
「登録の移転によって交付申請する場合」は、受講する必要はありません。
ここではヒッカケポイントがあるのでこの点は絶対注意してください!
個別指導では関連付けて理解するためにヒッカケポイントについて動画を用意しております!
【問3】農地法
農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。
>>折りたたむ
【解答】
X
原則、農業者が、自己所有の農地を農地以外に転用する場合、4条許可が必要です。
ただし、この農地が市街化区域内に属する場合は、
あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、4条許可までは必要ありません。
なので、×です。
本肢は「市街化調整区域」となってるので、例外には当たらず
原則通り、4条許可が必要ですね!