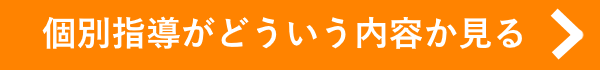【問1】代理
Aは、Bの代理人として、B所有の土地についてCと売買契約を締結したが、Aは無権代理人であった。
このことをCが知っていた場合でも、CはBに対し追認をするかどうか確答すべき旨催告することができ、
Bが確答をしないときは、Bは追認したものとみなされる。
>>折りたたむ
【解答】
X
B(本人)
A(無権代理人)
C(相手方:悪意)
①無権代理行為の相手方は、善意・悪意に関わらず、催告権はあります。
つまり、CはBに対し追認をするかどうか確答すべき旨催告することができます。
②次に、本人Bが「確答をしない」時は、「追認を拒絶」したものとみなされます。
この部分が本肢では誤りです。
上記2つは一緒に覚えておきましょう(^0^)/
【問2】罰則
取引士が業務上過失傷害の罪を犯し、10万円の罰金の刑に処せられた場合
当該取引士は、その登録を消除されることはない。
>>折りたたむ
【解答】
〇
取引士が登録消除されるのは、
1.不正手段によって登録を受けた、もしくは取引士証の交付を受けた場合
2.登録の欠格事由に該当する場合
3.事務禁止処分事由に該当し、特に情状が重い場合
4.事務禁止処分に違反した場合
「業務上過失傷害」による罰金刑は、上記に該当しないため登録消除されません。
もし、「傷害罪」による罰金刑を受けた場合は登録消除処分事由に該当します。
引っかかった方は注意してください!
【問3】国土利用計画法
市街化区域に所在する甲土地(面積2,500㎡)について、対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行わなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
X
「届出が必要な取引」の要件は、土地に関する①権利について、②対価の授受を伴って、③移転・設定する契約であることです。
①~③を満たす場合、事後届出の対象の取引となります。
「対価の授受を伴わない賃借権の設定」自体、②の対価の授受を伴っていないので
届出が必要な取引ではありません。
甲土地は2,500㎡の土地で届出面積に達していても届出対象の取引ではないので
事後届出が不要です。
基本的な問題ですが、上記以外の理解の仕方を知らないと、関連問題を間違えてしまいます。
「個別指導」では解き方・考え方をお伝えするため、
関連問題も得点できるようになります!
しっかり理解して本試験で得点できる実力を一緒に付けましょう!