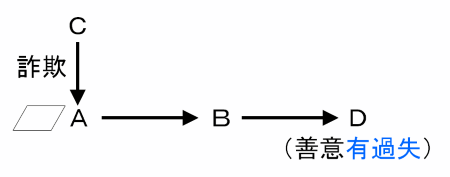【問1】詐欺
Aは第三者Cの詐欺により、A所有の土地をBに売却し、 Bは善意有過失のDに売却をし、移転登記もなされた。 その後、詐欺を原因として、AB間の売買契約が取消された場合、AはDに所有権を主張できる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
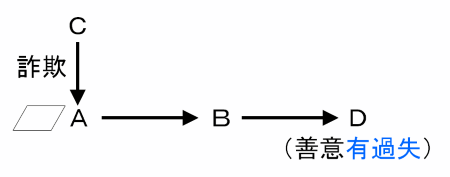
詐欺による取消しは、取消し前の善意無過失の第三者には対抗できません。
本肢は第三者Dが「有過失」なので、正しいです。
そして、この問題の解説をそのまま覚える方がいますが、それだと、すぐに忘れて実力は付きません。
キチンと理解することが重要です!
新しい事例として、「善意無過失の第三者E」と「詐欺を受けたA(上記Aと同じ)」を考えます。
まず、Aは詐欺を受けているのでかわいそうですね。
また、それを落ち度なく知らずに買って、その後、
取消されると第三者Eもかわいそうですよね。
そうすると、AとEのどちらがかわいそうかを考えるわけです。
Aは、詐欺を受けたものの、騙される側も多少は悪い(落ち度あり)ですよね。
一方、 Eは「Aが詐欺を受けていること」について落ち度なく知らない(善意無過失)です。
こう考えると、どちらを保護すべきですか?
過失なく何も知らないEを保護した方がいいですよね!
だから、Eを保護するわけです。
これを法律(ルール)にすると、「詐欺による取消し前の第三者が善意無過失の場合、善意無過失の第三者は保護される」となります。
言い換えれば、この第三者Eが悪意もしくは有過失であれば、第三者は保護されず、Aが保護されるというわけです。
理解しながらの方が楽しく勉強できますよね(^-^)/
【問2】クーリングオフ
宅建業者でない買主からクーリングオフによる売買契約の解除があった場合で、
この契約の解除が法的要件を満たし、かつ、売主Aが手付金を受領しているとき
Aは手付金から違約金を控除して返還することができる。
>>折りたたむ
【解答】
X
クーリングオフによる契約解除では、
違約金や損害賠償請求はされません!
これは重要なので覚えておいてください!
つまり、宅建業者に渡した手付金等は全部返ってきます!
「控除」って分かりますか?
簡単にいうと、「差し引いて」っていう意味です(^-^)/
【問3】開発許可
市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300㎡であるものについては、常に開発許可は不要である。
>>折りたたむ
【解答】
X
市街化調整区域はそもそも、市街化を抑制する区域です。
つまり、建物をできるだけ立てさせない区域です。
そのため、市街化調整区域においては、どれだけ小さい規模であっても原則、開発許可が必要となります。
つまり、300㎡の開発行為であっても原則許可は必要です。
したがって、「常に開発許可は不要」というのは誤りです。
ただ、これは理解が必要です。
単に「常に」という言葉から判断して誤りとするのでは、本試験の時に間違える可能性が高いです!
ヒッカケ問題でもひっかかるので、しっかり理解しましょう!
その点について個別指導で解説しています!
開発許可が必要かどうかを問う問題が出ればサービス問題と思ってください!
答えを導くプロセスを知っていれば、必ず得点できます!
▼値上げまであと2日です!
来年の合格を目指す個別指導!
分割払いの分割回数を増やし、支払いやすい内容となっています!
今すぐご確認ください!
↓
>>個別指導の詳細はこちら<<