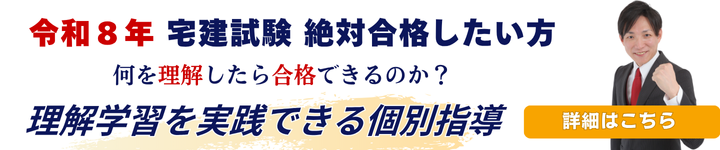【問1】保証
AとBはCに対して1000万円の連帯債務を負っており、各自の負担部分はそれぞれ500万円である。Aが800万円を弁済すれば、300万円を限度にBに対して求償できる。
>>折りたたむ
【解答】
×
連帯債務者が弁済したとき、他の連帯債務者に対して、
負担部分の「割合に応じて」求償することができます。
本肢では、AとBの負担割合は1:1なので
800万円のうち400万円を限度にBに対して求償できます。×
これは昨日お話した内容ですね!
連帯保証と連帯債務の「求償権」の違いです!
注意点は
連帯保証の場合、「負担部分を超えた部分」について求償でき
連帯債務の場合、「負担部分の割合に応じて」求償できる
という違いです。
もし、AとDが連帯保証人で、Bが主たる債務者だった場合、
Aが800万円を弁済すれば、負担部分を超える部分(500万円)は300万円なので、
Aは他の連帯保証人Dに対して300万円を求償できます。
【問2】免許基準
法人の役員のうちに業務上過失致死傷等の罪により3年間の懲役の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、判決に執行猶予がついていれば、直ちに免許を受けることができる。
>>折りたたむ
【解答】
×
法人の役員や政令使用人が欠格要件に該当する刑罰(禁錮刑以上の刑,暴力や宅建業法違反による罰金刑)に処された場合、
役員は欠格ですし、法人も欠格になります。
本問は懲役刑を受けているので、役員も法人も免許を受けることができません。
そして、執行猶予が付いていた場合はどうなるか?
執行猶予が「満了すれば」、直ちに免許を受けることができます。
本肢は、「執行猶予が付いていれば直ちに免許を受けることがでる」となっているので誤りです。
執行猶予満了までは待たないといけませんね!
基本問題ですが、凡ミスするような問題ですね!
ここで凡ミスをするようでは合格できません!
注意しましょう!
【問3】盛土規制法
盛土規制法によれば、宅地造成等工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域であって宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものについて指定される。
>>折りたたむ
【解答】
〇
宅地造成に伴い
「災害が生ずるおそれの大きい市街地
若しくは市街地となろうとする土地の区域
又は集落の区域」
が宅地造成等工事規制区域の対象です!
よって、〇です。
この部分を頭に入れておきましょう!
そして、
必要があると認めるときは、関係市町村長の意見を聴くことになっています。