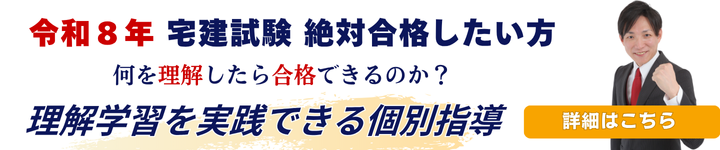【問1】弁済
AのBに対する貸金債務について、「金銭の受領の委任状」などの債権者である証書を持ったCが、債務の弁済を請求してきた。
しかし、Cは真の債権者ではなかった。そのことにつき、善意無過失のAはCに全額弁済してしまった場合、AはBに対する貸金債務の弁済を免れる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
弁済は本来債権者Bにしなければ、弁済は無効となります。
しかし、本当の債権者Bでなくてもそのような外観を備えていた者Cを信じて、
「善意無過失」でその者に弁済してしまった場合、その弁済は有効とされます。
ちなみに、弁済者Aから見て、債権者であるかのような外観を備えている者Cを「受領権者としての外観を有する者」といいます。
内容的には難しくないですが、参考にしていただければ幸いです!
↓
【問2】免許の要否
Aが宅地建物取引業を営もうとする場合において、Aが信託会社であるときは免許を受ける必要があるが、Aが信託業務を兼営する銀行であるときは免許を受ける必要はない。
>>折りたたむ
【解答】
×
信託会社や信託業務を兼営する金融機関が宅地建物取引業を営もうとする場合は
免許を受ける必要はありません。
これらの会社や金融機関は
国土交通大臣に届け出れば
「国土交通大臣免許」を受けたものとみなされます。
イメージとしては、「○○信託銀行」です。
免許が不要な者は誰でしょう?
①国、地方公共団体
②独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社
③信託会社・信託業務を兼営する銀行
この3種はまとめて頭に入れてきましょう!
【問3】都市計画法
都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には、都市計画に、地区計画を定めることができる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
地区計画を定めることができるのは、以下の2つの区域です
1.用途地域内
2.用途地域外でも、一定の要件をみたす満たす区域
したがって、用途地域が定められていない土地の区域であっても、
地区計画を定めることができる場合があるので正しい記述となります。
この一定の要件とは何か?と疑問に思うかもしれませんが、
出題される可能性は低いので覚える必要はありません!
無駄な勉強をせずに、必要な部分を頭に入れていきましょう!