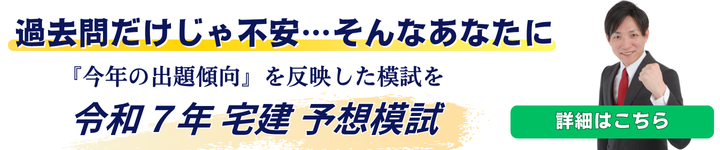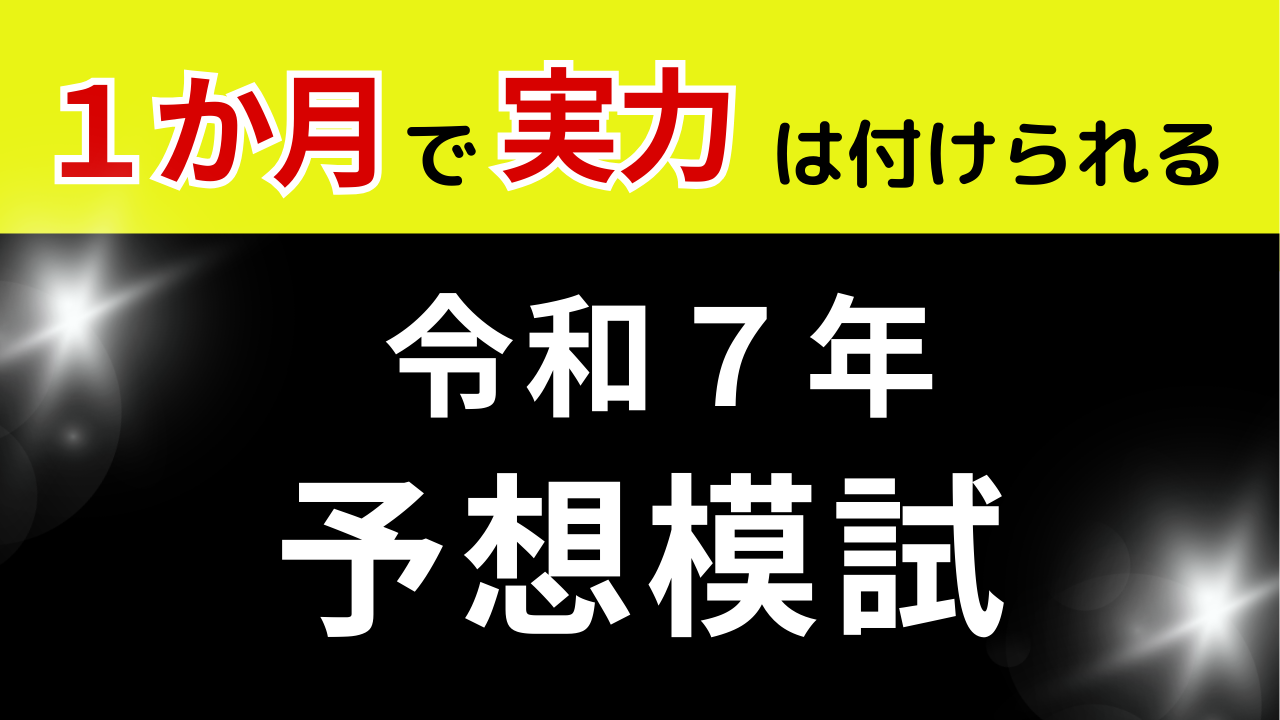【問1】不法行為
Aが所有する甲建物に塀を設置するために、Bに塀の設置を請け負わせた。
その後、Aは甲建物をCに賃借し、Cが占有しているときに、工事の瑕疵で塀が崩れ、第三者Dにケガをさせてしまった。
Bは、瑕疵を作り出したことに故意又は過失がなければ、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
A:所有者
B:請負業者(施行業者)
C:占有者
D:被害者
請負人に故意または過失がない場合、
請負人の工事により塀に瑕疵がある状態となったとしても、
請負人Bは不法行為責任を免れます。
■では、もし、請負人に故意もしくは過失があったら?
賠償した所有者もしくは占有者から求償されることになります(>_<)
つまり、賠償しないといけないわけです!
このように、1つの問題でも
宅建試験の範囲内で類題を学習できると効率的に勉強できますね!
【問2】罰則
宅建業者は、販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがある。
>>折りたたむ
【解答】
〇
「著しく事実に相違する表示」をすることは、誇大広告等に当たります。
誇大広告等の禁止に違反した場合、監督処分の対象となるほか、
6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金または併科に処せられることがあります!
なので、〇ですね!
罰則については、覚えるのが大変だと思います。なので、優先順位をつけて覚えていきましょう!
最優先で覚えるべき罰則は、下記6つの重い罰則です!
▼3年以下の懲役or300万円以下の罰金or併科
・不正の手段によって免許を受けた
・名義貸しの禁止の規定に違反して他人に宅建業を営ませた
・業務停止処分に違反して業務を営んだ
・無免許で事業を営んだ
▼2年以下の懲役or300万円以下の罰金or併科
・相手の判断に重大な影響を及ぼす事項を故意に告げなかった(事実告知義務違反)
▼1年以下の懲役or100万円以下の罰金or併科
・不当に高額の報酬を要求した(受領していなくても要求すること自体違反)
【問3】盛土規制法
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内における土地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
本問は正しい記述で、そのまま覚えればよいのです!
知事は、宅地造成等工事規制区域内の「土地の所有者、管理者又は占有者」に対して、
何を求めることができるのか?
「宅地の状況」や「宅地内の工事状況」について
報告してください!と求めることができます。