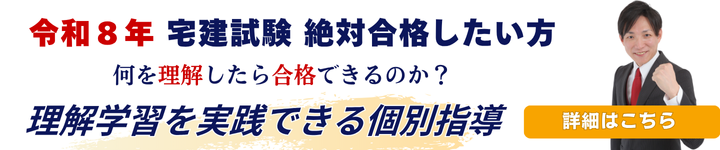こんにちは!レトスの小野です!
あなたは、どのような勉強の仕方をしていますでしょうか?
問題を解いたり、テキストを読んだりした時
「こういう場合はどうなるの。。。。。?」疑問を持つことはありませんか?
疑問を持つこと自体は悪いことではありません。
疑問を持つと言う事は、そのことに対して興味を持っているという現れです。
ただ、試験勉強では、これが自分の首をしめることになる場合があります。
実際に、これが原因で、落ちている方もたくさんいます。
理解しなくてもよい内容や、考えなくてもよい具体例まで考えてしまい
勉強が先にすすまなくなってしまう。。。。。
自分としては深入りすることで理解学習をしている気になって満足してしまいます。
この自分流の深入りした理解学習がズレた勉強となり合格のレールから外れてしまいます。
気になって進めない。。。。。。
テキストや過去問に記載されている内容をじっくり考え、
時間をかけて理解することは問題ないと思うのですが
そうではないことに時間をかけて考えてしまうクセがついている方は注意してください。
そして、私がお伝えしている理解学習は上記のような勉強ではありません。
理解すべき部分は理解する!
理解しなくてもよい部分は理解しない!
と割り切った勉強です。
そうすることで、短期間で、本試験で合格点を取るための勉強ができるんです。
まず、独学でできることというと、
「問題で質問されていない部分までは考えない」
これを実践しましょう!

【問1】不法行為
不法行為により物が毀損したことによる損害賠償の請求権の消滅時効の期間は、
権利を行使することができることとなった時から10年である。
>>折りたたむ
【解答】
X
一般的な債権の消滅時効は「権利行使できることを知ってから5年」または「権利行使できる時から10年」です!
これ基本なので、覚えておいてください!
そして本問は例外的な話です。
不法行為による損害賠償の請求権(物損の場合)は、
①「被害者またはその法定代理人」が「損害及び加害者を知った時から3年間」
行使しないときは、時効によって消滅します。
なので、×
また、②「不法行為の時から20年」を経過したときも権利が消滅します。
これをさらっと読み流すと痛い目に遭いますよ!
「損害」と「加害者」を知った時から「3年」
って書いてありますよね!
「損害」と「加害者」のどちらも知った時点から時効がスタートします!
例えば、物を壊されて加害者が誰か分かない場合は、
壊されたときからから3年経過しても、時効消滅しないわけです!
ただ、②のルールから、物を壊された時から「20年が経過」すると、損害賠償請求権は消滅します。
ここは、ヒッカケ問題が作りやすいんで、細かく覚えた方がいいですね!
そして、この問題の関連ポイントは非常に細かいので、個別指導で解説します!
この関連ポイントを頭に入れてないと、本試験で失点する可能性があるので、しっかり関連ポイントまで頭に入れましょう!
【問2】8種制限
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結した場合、Aが、Bから手付金600万円を受領する場合において、その手付金の保全措置を講じていないときは、Bは、この手付金の支払を拒否することができる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
まず、建築工事完了前の物件なので、手付金等が、代金の5%または1,000万円を超える場合に、保全措置が必要です。
本問の場合、3,000万円×5%=150万円
150万円を超える手付金等を受領する場合に「事前に」保全措置が必要ということですね!
そして、売主業者Aが保全措置を講じていない場合、買主Bは、
「保全措置をしていないなら手付金は払いません!」と支払い拒否をすることができます!
したがって○ですね!
【問3】盛土規制法
工事施行者とは、宅地造成、特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
>>折りたたむ
【解答】
〇
工事施行者については2パターンあります。それは「請負契約」による場合とよらない場合です。
請負契約による場合、工事施行者は、宅地造成工事の請負人(工事業者)となります。
一方、
請負契約によらない場合、自らが造成工事を行う場合なので、自らが工事施行者となります。
例えば、工事業者が土地を所有して、その土地を自らが造成する場合、この工事業者は工事主でもあり工事施行者でもあるわけです。