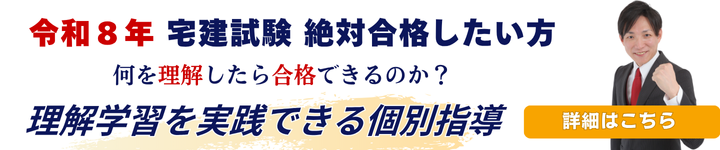【問1】不動産登記法
表題部所有者について住所の変更があったときは、当該表題部所有者は、その変更があったときから1月以内に、当該住所についての変更の登記の申請をしなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
×
・建物が滅失した場合
・土地の地目の変更があった場合
・表題登記がない建物(マンション以外)の所有権を取得した場合
その日から、「1ヶ月以内」にそれぞれの登記しないといけません。
しかし、
「表題部所有者の氏名や住所を変更した場合」
この場合の変更登記は、申請時期が定められていません。×
先日の問題の解説を読んだ方は絶対正解してもらいたいです!
【問2】案内所
宅地建物取引業者Aが一団の宅地建物の分譲を行う場合、Aが、契約行為等を行わない案内所に置かなければならない成年者である専任の宅建士の数は1名以上でなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
×
案内所で専任の取引士を置かなければならないのは、
案内所で、申込を受けたり、契約したりする場合だけです。
つまり、案内所で、上記のことを行わないのであれば、専任の取引士は不要なんです!
試験作成者はこの当たりを狙いそうですね♪
■案内所とクーリングオフとのつながり
【問3】国土利用計画法
停止条件付きの土地売買等の契約を締結した場合には、停止条件が成就した日から起算して2週間以内に事後届出をしなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
×
事後届出は「契約締結日」から2週間以内にしなければなりません。
つまり、停止条件が「成就してから」ではなく、
土地売買等の「契約を締結した日から」2週間以内に届出が必要です。
非常に重要なことをお伝えします!
それは「知っている知識を基に答えを導く!」ということです。
宅建試験では受験生をヒッカケルために色々な条件を付けたり、
法律にないルールを勝手に作って出題したりしてきます!
そういった問題に対応する方法が
「知っている知識を基に答えを導く!」ということです。
本問で言えば、
「事後届出は契約締結してから2週間以内に行う」
という基本的なルールがありますよね!
この基本的なルールを使って答えを導くわけです。
つまり、
『停止条件が付いている場合、「成就してから」ではなく、
土地売買等の「契約を締結した日から」2週間以内に届出が必要』
と覚える必要はないわけです。
基本ルールに基づけば、答えは導けますよね!
これは日ごろの勉強でも習慣化してほしい内容です!
もし、この考え方で間違えた場合は、
その時、新しいルールを覚えればそれでいいわけです!