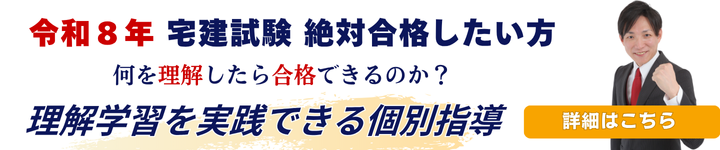【問1】債権譲渡
AはBに対する金銭債権をCに譲渡した。債権譲渡についてBはCに対して確定日付のない書面で承諾をした場合、Cは第三者Dに対して自分が債権者であることを主張できる。
>>折りたたむ
【解答】
×
債権譲渡について、第三者に対抗するには、「債務者の承諾」もしくは「譲渡人Aから債務者への通知」どちらも、「確定日付のある証書」で行う必要があります。
■昨日と同じ動画ですが、不安があれば再度ご確認ください!
【問2】案内所
宅地建物取引業者Aが一団の宅地建物の分譲を行う場合について、Aは分譲の代理を他の宅地建物取引業者Bに依頼した。
Bは単独でその分譲のために現地案内所を設置した場合、案内所においては、Bのみ標識を掲示すればよい。
>>折りたたむ
【解答】
〇
案内所に標識を掲示する義務があるのは、「案内所を設置する宅建業者」です。
分譲会社は、現地(分譲地)に標識を掲示します。
基本的なことですが、覚えられていない方も多いです。
また、問題文はしっかり読んでください。
読み違いで間違えるのはもったいないです!
この問題で重要なのは、「問題の読み方」です!
↓
【問3】農地法
市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
>>折りたたむ
【解答】
×
市街化区域内の耕作目的での農地の取得は3条の許可が必要です!
届出だけでよいという特例は適用されません。
市街化区域内の特例は4条5条だけですね!
なぜでしょう?
そもそも市街化区域は、ドンドン建物を建てていく区域なので、
建物を建てて欲しい区域と言えます!
言い換えると、「農地→宅地」を促進させる区域とも言えます。
つまり、「転用」においては、制限を緩めても構わないということです。
転用とは4条と5条ですよね!
それゆえ、4条と5条では許可までは必要なく、届出でよいとしています!
そして、転用に関係ない3条は制限に変更はないということです。
「市街化区域」=「ドンドン建物を建てていく区域」
というイメージからこの問題の答えを導けるわけです!