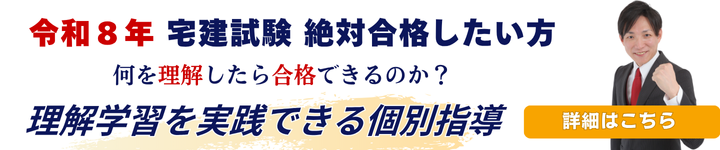【問1】不法行為
不法行為により物が毀損したことによる損害賠償の請求権の消滅時効の期間は、 権利を行使することができることとなった時から10年である。
>>折りたたむ
【解答】
×
一般的な債権の消滅時効は「権利行使できることを知ってから5年」または「権利行使できる時から10年」です!
これ基本なので、覚えておいてください!
そして本問は例外的な話です。
不法行為による損害賠償の請求権(物損の場合)は、
①「被害者またはその法定代理人」が「損害及び加害者」を知った時から3年間」 行使しないときは、時効によって消滅します。
なので、×
また、②「不法行為の時から20年」を経過したときも権利が消滅します。
これをさらっと読み流すと痛い目に遭いますよ!
「損害」と「加害者」を知った時から「3年」
って書いてありますよね!
「損害」と「加害者」のどちらも知った時点から時効がスタートします!
例えば、物を壊されて加害者が誰か分かない場合は、 壊されたときからから3年経過しても、時効消滅しないわけです!
ただ、②のルールから、物を壊された時から「20年が経過」すると、損害賠償請求権は消滅します。
■上記は「物損」の話ですが、「人損」の場合は上記①の3年が5年となります。
つまり
①「被害者またはその法定代理人」が「損害及び加害者」を知った時から5年間」 行使しないときは、時効によって消滅します。
または
②「不法行為の時から20年」を経過したときも権利が時効消滅します。
(②は物損も人損も同じです。)
【問2】8種制限
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結した場合、Aが、Bから手付金600万円を受領する場合において、その手付金の保全措置を講じていないときは、Bは、この手付金の支払を拒否することができる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
まず、建築工事完了前の物件なので、手付金等が、代金の5%または1,000万円を超える場合に、保全措置が必要です。
本問の場合、3,000万円×5%=150万円
150万円を超える手付金等を受領する場合に「事前に」保全措置が必要ということですね!
そして、売主業者Aが保全措置を講じていない場合、買主Bは、
「保全措置をしていないなら手付金は払いません!」と支払い拒否をすることができます!
したがって○ですね!
▼では、本肢の場合(未完成物件3000万円、手付金600万円)、
手付金額の制限に違反しているでしょうか?
手付金額の制限では、「代金の2割を超える手付金を受領してはならない」となっています。
代金の2割=600万円です。
「超える」というの、その数字は含みません!
つまり、600万円は違反ではなく、601万円は違反する
ということです!
▼超、以上、以下、未満
超・未満はその数字を含みません!
以上・以下はその数字を含みます!
600万円超:601万円、602万円・・・
600万円以上:600万円、601万円・・・
600万円以下:600万円、599万円・・・
600万円未満:599万円、598万円・・・
【問3】土地区画整理法
土地区画整理組合が成立した場合において、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者はすべて組合員となるが、施行地区内の借家人は組合員とはならない。
>>折りたたむ
【解答】
〇
借家人は組合員とはなりません。
なぜでしょう?
そもそも土地区画整理事業って、
ごちゃごちゃした「土地」をきれいに整理する事業です。
つまり、土地に関する事業だからです!
建物は関係ないですね!