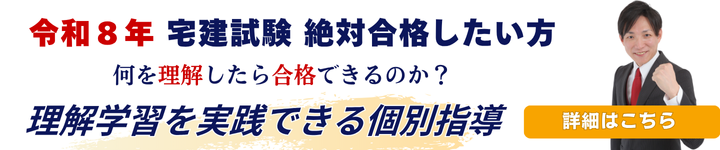【問1】債務不履行
A所有の建物につき、Aを売主、Bを買主とする売買契約が成立し、 移転登記後引渡前に、地震により建物が滅失してしまった。 この場合、両者の責に帰すことができない場合、買主Bは売主Aからの代金の請求を拒むことができない。
>>折りたたむ
【解答】
×
契約が成立して引渡しをする前に、
どちらの責任でもない事由(例えば、地震)で目的物が滅失した場合、
①買主は、代金支払いを拒絶することができます。
よって、「買主Bは売主Aからの代金の請求を拒むことができない。」という記述は誤りです。
②また、買主Bは「契約解除」もできます。
③そして、解除することで、初めて、買主の代金支払い義務も消滅するので
①~③まで頭に入れておきましょう!
【問2】事務所
「事務所」とは、本店又は支店やその他の政令で定めるものを指すものであるが、宅地建物取引業を行わず他の兼業業務のみを行っている支店は「事務所」に含まれない。
>>折りたたむ
【解答】
〇
ここは間違えやすいので、整理します。
宅建業を行っている本店、支店は、ともに「事務所」です。
では、
本店:宅建業を営んでいる
支店:宅建業を営んでいない
場合はどうなるか?
この場合、
本店:事務所
支店:事務所ではない・・・本肢の問題
次に、逆の場合を考えましょう!
本店:宅建業を営んでいいない
支店:宅建業を営んでいる
場合はどうなるか?
本店、支店ともに「事務所」です。
この点は間違えやすいので注意してください!
分かりにくい方はこちら
↓
https://takken-success.info/e-2/
【問3】土地区画整理法
土地区画整理法による建築行為等の規制に違反して建築された建築物等については、施行者は、事業の施行のため必要となったときはいつでも移転又は除却をすることができる。
>>折りたたむ
【解答】
×
建築行為等の規制に違反して建築された建築物は、邪魔ですよね・・・
この場合、
「都道府県知事等」は、相当の期限を定め、必要な限度において
原状回復、又は、移転・除却が命ずることができます!
主語と述語に注意してください!
主語と述語を押さえることで問題文全体を理解し、
そのご、細かい内容を理解し
それが正しいかどうかを判断していく必要があります。
問題文全体(主語、述語、修飾語)で言えば、
「施行者はいつでも除去できる」となっています。
これは誤りです。
今回でいうと
「知事は除去を命じることができる」
そして、知事から命じられたから、施行者は除去できるわけです。
主語述語を少し変えるだけで、問題文の内容が変わってくる場合があるので
そのようなひっかけ方は、他の法令制限でもよくありますし、宅建業法でもよくあります。
そのため、しっかり、主語と述語を押さえましょう!
「誰が」何をしたのか?
これは問題を把握する上で最々々重要です。