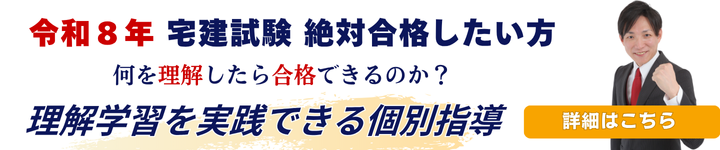一方は「これで十分だ」と考えるが、
もう一方は「まだ足りないかもしれない」と考える。
そうしたいわば紙一枚の差が、
大きな成果の違いを生む。
パナソニックの創業者である松下幸之助さんの言葉です。
例えば、Aさんは1日10問勉強して、これで十分だと考えました。
一方、Bさんは1日10問勉強して、まだ足りないかもしれないからあと2問だけやろう!
と考えて、12問行いました。
1日2問の違いです。
でも、これが1か月経てば、60問の違いになり
3か月経てば、180問の違いになり
試験日には、360問もの大きな違いになっています。
これまでの過ぎた時間は取り戻せませんが
これからの時間は変えられます!
今日一日、「まだ足りないかもしれない」という気持ちを持って頑張っていきましょう!
私自身も、受験生だったとき、どれだけ勉強しても不安だったので
あと少し頑張ろうという気持ちを持って毎日勉強していました!
【問1】取得時効
Aが善意無過失で8年間所有の意思をもって、平穏かつ公然に他人のものを占有し、AがBに賃貸し、Bが2年間占有した。
この場合、Aは取得時効を主張できない。
>>折りたたむ
【解答】
×
自らが占有する場合でなく、賃借人により間接的に占有する場合も、
Aが所有の意思をもっていれば、取得時効を主張できます。
つまり、本肢では、合計10年経過しているので、取得時効を主張できます。
基本事項なので、覚えてくださいね!
間接占有も自己占有に含まれるということですね!
個別指導受講者は合格テキストP26の真ん中あたりを確認しましょう!
【問2】重要事項説明
建物の買主Bが宅建業者であり、当該建物の近所に事務所を構えており、その建物に関する事項を熟知している場合、宅建業者は、Bに対して重要事項説明書を交付すれば重要事項の説明を行うことなく、売買契約を締結することができる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
重要事項の説明は買主や借主に対して行わないといけません。
ただし、買主や借主が宅建業者の場合は、重要事項「説明」は省略できます!
しかし、35条書面の「交付」は、必要なので注意しましょう!
「35条書面を交付すれば、重要事項説明は省略できる」ということです!
【問3】土地区画整理法
土地区画整理法による建築行為等の規制に違反して建築された建築物等については、施行者は、事業の施行のため必要となったときは、いつでも移転又は除却をすることができる。
>>折りたたむ
【解答】
×
建築行為等の規制に違反して建築された建築物は、邪魔ですよね・・・
この場合、
「都道府県知事等」は、相当の期限を定め、必要な限度において
原状回復、又は、移転・除却が命ずることができます!
主語と述語に注意してください!
主語と述語を押さえることで問題文全体を理解し、
そのご、細かい内容を理解し
それが正しいかどうかを判断していく必要があります。
問題文全体(主語、述語、修飾語)で言えば、
「施行者はいつでも除去できる」となっています。
これは誤りです。
今回でいうと
「知事は除去を命じることができる」
そして、知事から命じられたから、施行者は除去できるわけです。
主語述語を少し変えるだけで、問題文の内容が変わってくる場合があるので
そのようなひっかけ方は、他の法令制限でもよくありますし、宅建業法でもよくあります。
そのため、しっかり、主語と述語を押さえましょう!
「誰が」何をしたのか?
これは問題を把握する上で最々々重要です。