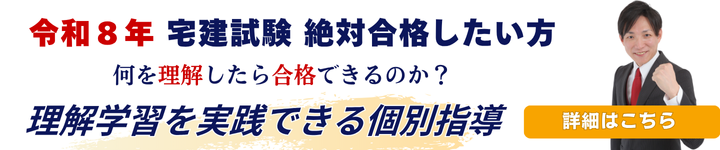令和7年度 宅建業法の法改正情報
1. 国土交通大臣免許の申請先の変更
この改正のポイント: 国土交通大臣免許の申請手続が都道府県知事を経由せずに、直接行えるようになりました。
【改正前】
- 国土交通大臣免許を申請する場合、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、申請書類を提出する必要がありました。
- たとえば、東京に主たる事務所がある事業者が大臣免許を申請する場合、「東京都知事」を経由して国土交通大臣に書類を送る仕組みでした。
- この経由制度により、書類提出から処理までに時間を要し、手続が煩雑になりがちでした。
【改正後】
- 国土交通大臣免許を申請する者は、直接、主たる事務所の所在地を管轄する国土交通省地方整備局に申請書を提出できるようになりました。
- 都道府県知事を経由する手続は廃止され、よりスピーディかつ効率的に申請が可能になります。
【具体例】
以前は、北海道と大阪に事務所を持つ宅建業者が大臣免許を取得しようとする場合、主たる事務所が札幌であれば、「北海道知事」を経由して申請する必要がありました。
改正後は、北海道開発局(地方整備局)に直接申請することで完了します。
【実務上のメリット】
- 手続きの迅速化: 書類のやり取りが一本化され、許可までの時間が短縮される。
- 事務コストの軽減: 都道府県と国の間で重複していた事務作業が削減。
- 電子申請との連携も期待: 今後のデジタル化の流れに沿った制度改善。
【注意点】
- 「主たる事務所」の所在地を正確に確認し、その管轄の地方整備局名を把握しておく必要があります。
- 書類の提出方法(郵送・持参・オンライン等)は整備局によって異なる場合があるため、事前確認が重要です。
【背景・目的】
これまでの都道府県知事経由の仕組みは、全国をまたぐ大臣免許業者にとって時間的・事務的な負担となっていました。
今回の改正は行政手続きの簡素化・効率化を目的としており、国全体でのデジタルガバメント推進の一環とも言えます。
2. 案内所等の届出の申請先の変更
この改正のポイント: 国土交通大臣免許を持つ宅建業者が案内所等を設置する際の届出先が変更され、都道府県知事を経由せず、直接地方整備局に提出できるようになりました。
【改正前】
- 案内所やモデルルームなどを開設する場合、その所在地の都道府県知事を経由して、国土交通大臣に届出を行う必要がありました。
- たとえば、東京に本店、大阪に案内所を設置する場合、大阪府知事を経由して届出。
- 経由手続により、届出の処理に時間と手間がかかっていました。
【改正後】
- 案内所の届出は、所在地に関係なく、主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局に「直接」届出することになります。
- 経由制度は廃止され、申請の手続きが一本化されました。
【具体例】
宅建業者A社(本店:福岡)が、東京に新しくモデルルーム(案内所)を開設する場合:
- 改正前: 東京都知事を経由して国土交通大臣に届出
- 改正後: 九州地方整備局(本店所在地である福岡を管轄)に直接届出
【実務上のメリット】
- 手続の迅速化: 書類が都道府県を経由しないため、処理が早くなります。
- 届出先が一本化: 地方整備局に集約されることで、事務負担が軽減されます。
- 広域展開する企業に有利: 各都道府県に対する届出手続が不要となり、全国展開する企業にとって特にメリットが大きいです。
【注意点】
- 「案内所等」とは、契約締結の場となるような事務所、モデルルーム、現地販売センターなどを含みます。
- 届出様式や必要書類は、各地方整備局のWebサイト等で確認が必要です。
- 都道府県知事免許業者は、引き続き都道府県への届出が必要ですので、免許の種別による届出先の違いに注意しましょう。
【背景・目的】
従来の「都道府県知事経由」の制度は、業務の重複や処理の遅延を生んでいました。
今回の改正は、届出制度の合理化・迅速化を図るものであり、国の行政手続デジタル化の流れにも合致しています。
3. 専任宅建士の証明書の提出が不要に
この改正のポイント: 宅建業の免許申請等において、専任の宅地建物取引士に関する2種類の証明書の提出が不要になりました。
【これまで必要だった証明書】
- ① 身分証明書: 本籍地の市区町村で発行される、公民権の停止などの情報が記載された証明書。
- ② 登記されていないことの証明書: 法務局が発行し、成年被後見人等でないことを証明する書類。
【改正前】
- 宅建業の免許申請(新規・更新・変更)を行う際には、上記2つの証明書を専任の宅建士ごとに提出する必要がありました。
- 複数の事務所を運営する業者では、証明書の取得・管理が煩雑で、申請のたびに本籍地の役所や法務局に出向く必要がありました。
【改正後】
- 免許申請において、専任宅建士の身分証明書および登記されていないことの証明書の提出は不要となりました。
- ただし、本人確認や要件確認は引き続き行われるため、虚偽申請を行った場合の罰則は変わりません。
【実務上のメリット】
- 申請手続の簡素化: 証明書取得のために複数の窓口に行く必要がなくなり、時間と労力が削減。
- コスト削減: 証明書の発行手数料や郵送費、委任状の作成等が不要に。
- 事務負担の軽減: 支店・営業所を多数持つ業者では、大きな効率化につながります。
【注意点】
- 証明書提出が不要になったとはいえ、専任宅建士としての欠格要件は変わりません。
- 万一、欠格要件に該当している者を専任宅建士として届け出た場合、免許取消などの行政処分対象となります。
- 本人の誓約書や業者側のチェック体制が、これまで以上に重要になります。
【背景・目的】
この改正は、行政手続きの合理化・負担軽減を目的としたものです。
「登記されていないことの証明書」や「身分証明書」は、提出先の自治体や法務局によっては取り寄せに時間がかかるなど、業者にとって大きな負担となっていました。
今後は、自己申告+後からのチェック体制で対応し、国全体の行政手続きのデジタル化にも貢献する形となります。
4. 宅建業者名簿への専任宅建士の氏名記載が不要に
この改正のポイント: 宅建業者ごとに作成・管理されている「宅建業者名簿」において、専任の宅地建物取引士(宅建士)の氏名の記載が不要となりました。
【改正前】
- 宅建業者名簿には、事務所ごとに配置されている専任の宅建士の氏名を記載することが義務付けられていました。
- たとえば、A社が3つの支店を持ち、それぞれに1名ずつ専任宅建士を配置している場合、名簿に3名の氏名を記載する必要がありました。
- 異動や退職、新たな配置があるたびに、名簿の内容を更新・修正しなければならず、手間がかかっていました。
【改正後】
- 宅建業者名簿への「専任宅建士の氏名」の記載は不要となり、事務所単位での氏名管理は求められなくなりました。
- ただし、専任宅建士の設置義務そのもの(事務所ごとに1名以上)は引き続き必要です。
【実務上のメリット】
- 名簿管理が簡素化: 専任宅建士の異動・変更に伴う名簿修正が不要に。
- プライバシー保護の向上: 氏名が不要となったことで、宅建士個人の情報が外部に記載・公開されにくくなりました。
- 業者の事務負担軽減: 支店・営業所が多い業者にとって、管理業務が大幅に効率化されます。
【注意点】
- 記載義務がなくなっただけであり、専任宅建士を配置しなければならない義務自体は存続しています。
- 宅建業者は、内部で誰がどの事務所の専任宅建士かを把握・管理しておく必要があります。
- 監督官庁による立入検査や指導があった場合、速やかに専任宅建士の情報を提示できるようにしておくべきです。
【背景・目的】
この改正は、行政手続きの簡素化と、個人情報の保護を両立させる目的で行われました。
名簿に個人名を記載することで、名簿の写しが関係者に開示される場面において、本人の意図しない情報公開が起きる懸念がありました。
改正後は、必要な情報だけを簡潔に管理する仕組みに移行しつつ、実効性を保つ制度となっています。
5. 従業者名簿への性別・生年月日の記載が不要に
この改正のポイント: 宅建業者が作成・備え付ける「従業者名簿」において、性別および生年月日の記載義務が廃止されました。
【従業者名簿とは?】
宅建業者がその事務所に勤務するすべての従業者について、氏名・役職・宅建士資格の有無・雇用開始日などを記載して作成・備え付ける帳簿のことです。
【改正前】
- 従業者名簿には、以下の情報が全員分必要でした:
- 氏名
- 性別
- 生年月日
- 雇用開始日
- 職務内容
- 宅建士登録の有無 など
- 性別・生年月日を記載する際に個人情報保護の観点から取り扱いに注意が必要でした。
【改正後】
- 性別・生年月日の記載が不要となりました。
- 氏名や職務内容、宅建士であるかどうかなど、業務に直接関係する項目のみ記載すればOKとなりました。
【実務上のメリット】
- 個人情報保護の強化: 不要な個人情報の収集・管理を避けることができ、トラブル防止につながります。
- 名簿作成・管理の効率化: 記載項目が減り、事務作業が簡素化されます。
- 人事異動や雇用管理がしやすくなる: 特にパート・アルバイト等を含めた大量の従業員を管理する場合に効果大。
【注意点】
- 記載不要=把握しなくてよいという意味ではありません。必要に応じて本人確認資料等をもとに適切に管理する必要があります。
- 監督官庁による立入検査時には、宅建士の資格有無や職務内容など、その他の必須項目が適切に記載されているかが確認されます。
- 名簿様式を紙やExcelなどで独自に運用している場合は、旧様式のまま性別・生年月日を記入し続けていないか注意が必要です。
【背景・目的】
この改正は、個人情報の保護と業務の効率化を目的としたものです。
近年、性別や生年月日といった個人情報は、法的にも慎重な取り扱いが求められる情報とされており、
宅建業においても、業務上不要な情報は原則として取得しない方向へと制度が見直されました。
6. 標識への専任宅建士の氏名記載 → 「人数」の記載に変更
この改正のポイント: 宅建業者が事務所に掲示する「標識」について、これまで必要だった専任宅建士の氏名の記載が不要人数を記載するルールへと変更されました。
【改正前】
- 宅建業者は、事務所ごとに以下の情報を標識(いわゆるプレート)として掲示する義務がありました。
- その中に、「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」の記載も含まれていました。
- 氏名の掲示により、従業員の異動や退職・採用のたびに標識の作り直しが必要となり、業者にとって手間とコストがかかっていました。
【改正後】
- 専任宅建士の氏名の記載は不要となり、代わりに以下の内容を掲示します:
- 専任宅建士の人数
- 宅建業に従事する者の人数
- 事務所の代表者(政令で定める使用人)の氏名
- 今後は、個人名ではなく人数ベースでの掲示となるため、内容変更の頻度が大幅に減少します。
【実務上のメリット】
- 標識の作り直しが不要: 氏名ではなく人数を記載するため、異動・退職による更新が不要。
- コスト削減: 新たな標識作成・設置の手間と費用が大幅に軽減。
- プライバシー保護: 氏名の掲示が不要になり、従業員の個人情報漏洩リスクが軽減。
【注意点】
- 「人数」の記載であっても、実態と一致していなければ違反になります。
- 専任宅建士の人数や宅建業従事者の人数は、常に最新の正確な情報を掲示しておく必要があります。
- 掲示義務がある事務所(本店、支店、案内所等)ごとに、標識の掲示が必要です。
- 政令で定める「事務所の代表者(使用人)」の氏名は、引き続き掲示が必要です。
【背景・目的】
この改正は、業者の負担軽減と個人情報の保護を両立するために行われたものです。
氏名の掲示は、情報漏洩リスクやプライバシー保護の観点から問題視されることが増えており、
また標識を頻繁に更新する必要があることで、事務負担・コストの増加にもつながっていました。
今後は、業務実態を正確に示しつつ、簡潔な情報提供を図る形式へと制度がシフトしています。
7. デジタルサイネージによる掲示が可能に
この改正のポイント: 宅建業者の事務所における「報酬額」および「標識」の掲示義務について、従来の紙媒体だけでなく、デジタルサイネージ(電子表示)による掲示が認められるようになりました。
【改正前】
- 宅建業者は、事務所内に以下の情報を紙などの物理的媒体で掲示しなければなりませんでした:
- 報酬額に関する掲示(仲介手数料など)
- 標識(免許番号、免許年月日、代表者名、宅建士の人数など)
- 掲示方法としては、紙に印刷して壁に貼る、額縁に入れて受付に置くなどが一般的でした。
【改正後】
- これらの掲示について、デジタルサイネージ(モニターや電子ディスプレイ)による表示が認められるようになりました。
- 条件としては、常時、誰が見ても明確に確認できる状態で表示されていることが求められます。
【デジタルサイネージとは?】
液晶ディスプレイやタブレット、モニター等を活用して、映像や静止画を電子的に表示する設備のことです。近年では、店舗の案内表示や広告などにも広く使われています。
【実務上のメリット】
- 店舗の雰囲気に合わせたスマートな掲示が可能: 受付やエントランスにすっきりとした印象を与えることができます。
- 表示内容の更新が容易: 紙の差し替えや再印刷が不要になり、データ更新だけで済みます。
- 多言語表示にも対応しやすい: 外国人来客がある事務所では、言語を切り替えて表示可能。
- DX(デジタルトランスフォーメーション)推進: 不動産業界のIT化の流れに対応できます。
【注意点】
- 常時表示されていることが前提です。スリープ状態やスライドショー方式で一定時間しか表示されない場合は違反とみなされる可能性があります。
- 画面が小さすぎて文字が読めない、または設置場所が不適切で来客者から確認できない場合も違反となるおそれがあります。
- 停電や機器故障時のバックアップ掲示についても、トラブル時の対応を考慮しておくべきです。
【背景・目的】
この改正は、デジタル社会への対応と、事業者の利便性向上を目的としたものです。
近年、業界全体でペーパーレス化やIT活用が進む中で、掲示方法にも柔軟性を持たせることが求められていました。
デジタルサイネージの活用により、見やすく・管理しやすく・洗練された事務所環境の実現が可能になります。
8. 媒介契約の登録事項が追加
この改正のポイント: 宅地建物取引業者が締結した媒介契約に基づき、指定流通機構(レインズ)へ登録する際の項目として、「取引の申込みの受付状況」の情報を新たに登録することが義務化されました。
【改正前】
- 媒介契約を締結した際、宅建業者は指定流通機構(例:レインズ)に物件情報を登録する義務がありました。
- 登録項目には、「物件の所在地」「価格」「土地・建物の概要」などの基本情報が含まれていましたが、購入申込みの状況までは登録不要でした。
【改正後】
- 上記の基本情報に加え、「取引の申込みの受付に関する状況」を登録する項目が新設されました。
- 登録時に選択すべき状態は、以下の3つから選ぶ形式です:
- 公開中(申込みはまだない)
- 書面による購入申込みあり(買付証明書等を受け取っている)
- 売主都合で一時紹介停止中(内見・案内を一時停止している)
【実務上のメリット】
- 取引の透明性が向上: 他の宅建業者が状況をリアルタイムで把握でき、無駄な紹介や申込みの重複を回避できます。
- 情報提供の質が向上: 購入希望者に対して、現在の交渉状況を正確に伝えやすくなります。
- 媒介業者間の連携がスムーズに: 取引状況の共有が進むことで、トラブルやクレームの防止につながります。
【注意点】
- この登録は義務です。情報が欠けている場合、レインズ側で登録が完了しない可能性があります。
- 状況が変化した場合(例:申込みが入った/申込みがキャンセルされた等)、速やかに更新する必要があります。
- 誤ったステータスを登録していた場合、取引関係者への影響が大きく、信頼失墜にもつながりかねません。
【背景・目的】
この改正は、宅地建物取引における情報の的確な共有と、成約までのスムーズな流れを目的としています。
従来は、表向き「公開中」となっていても、実際には申込み済であるケースが多く、内見予約や交渉が無駄に終わる事例が多発していました。
今回の改正により、物件情報の正確性とタイムリーな更新が求められ、取引の効率化と顧客満足度の向上が期待されています。
9. 低廉な空家等(800万円以下)の特例:売買・交換の媒介
この改正のポイント: 空家対策として、価格が低い物件の取引を促進するため、仲介業者(宅建業者)が得られる報酬の上限が引き上げられました。
【改正前】
- 対象物件:400万円以下の物件
- 売主から受領できる報酬の上限:
- 「通常の報酬額」+「現地調査等の費用」の合計額
- または「18万円(消費税込で19万8000円)」のいずれか低い方
- 買主から受領できる報酬:特例なし(通常の上限のみ)
【改正後】
- 対象物件:800万円以下の空家等
- 売主・買主の両方から受領できる報酬の上限:各33万円(税込)
- つまり、合計で最大66万円(税込)まで受領可能
【注意点・条件】
- この特例を適用するには、媒介契約時に依頼者に説明し、事前に合意を得ておく必要があります。
- 説明と同意がない場合は、この特例を使うことはできません。
- 従来よりも報酬額が大きくなるため、説明責任がより重要になります。
【具体例】
宅建業者A社が、築45年・売買価格600万円の一戸建てについて、売主・買主の双方から媒介の依頼を受けたとします。
A社は、媒介契約の締結時に特例制度について説明し、双方の合意を得ました。この場合、A社が受け取れる報酬額は以下のとおりです:
- 売主から:33万円(税込)
- 買主から:33万円(税込)
- 合計:66万円(税込)(この金額が上限)
【背景・目的】
近年、空家の増加が社会問題となっており、特に地方部や老朽化物件は、売却しても仲介手数料が見合わず、宅建業者が扱いたがらないという現実がありました。今回の改正により、取引価格が低くても業者が一定の報酬を得られるようになり、空家の流通が進むことが期待されています。
10. 低廉な空家等(800万円以下の物件)の特例:売買・交換の「代理」
この改正のポイント: 800万円以下の空家等の売買・交換における代理契約について、宅建業者が受領できる報酬額の特例が新たに設けられました。
【「代理」とは?】
ここでの「代理」とは、宅建業者が売主または買主の名において契約を締結する形態(=代理権限を受けて行動する)を指します。
一般的な「媒介」(あっせん・仲介)とは異なり、宅建業者自身が当事者と同じ立場で契約を結ぶため、報酬体系も異なります。
【改正前】
- 対象物件:400万円以下の空家・低廉な物件
- 売主から受領できる報酬額の上限:
- 「通常の報酬額」+「現地調査等に要する費用」
- または18万円(消費税込19万8,000円)
- 上記のいずれか低い金額
- 買主から受領できる報酬額:特例なし(通常の上限)
- 売主・買主の合計上限は特に定められていなかった
【改正後】
- 対象物件:800万円以下の空家・低廉な物件
- 売主から受領できる報酬額の上限:66万円(税込)
- 買主から受領できる報酬額の上限:66万円(税込)
- ただし、売主・買主の合計で66万円(税込)までが上限となります。
【具体例】
宅建業者B社が、売主Cの代理人として、800万円の空家の売買契約を締結した場合:
- 売主Cから報酬:最大66万円(税込)
- 同時に買主からも報酬を受け取る場合、売主と買主を合わせて66万円(税込)以内である必要があります。
- 例:売主から30万円、買主から36万円 → 合計66万円 → 適法
- 例:売主から40万円、買主から40万円 → 合計80万円 → 違反(超過)
【実務上のメリット】
- 代理契約でも収益性を確保しやすくなった: 取引価格が低くても、実費を回収できるだけの報酬設定が可能に。
- 空家対策の強化: 老朽空家など、従来は「採算が合わない」として敬遠されがちだった物件も、対応しやすくなる。
- 価格によらない柔軟な取引対応: 顧客の代理人として積極的に動くことができ、機会損失を防げる。
11. 長期の空家等の貸借の「媒介」の特例
この改正のポイント: 長期間使用されていない空家等を対象とする賃貸借の媒介について、宅建業者が貸主から通常の2倍の報酬を受け取ることができる特例が新設されました。
【対象となる物件】
- 長期の空家等であることが条件です。
- 具体的には:
- 現に1年以上使用されていない宅地建物
- または、将来にわたって使用の見込みがない宅地建物
【報酬の上限(改正内容)】
- 通常: 貸主・借主の双方から合計して借賃の1.1か月分が上限(各0.55か月分)
- 改正後の特例: 下記の条件を満たせば、
- 貸主から借賃の2.2か月分まで受領可能
- 借主からの報酬は不可(貸主から全額受け取る場合)
- または、貸主+借主の合計で最大2.2か月分まで受領可能
【特例適用の条件】
- 媒介契約を締結する際に、貸主(依頼者)に対して特例報酬の説明を行い、同意を得ることが必要です。
- 書面での同意が望ましく、後日のトラブル回避のため媒介契約書に明記するのが適切です。
【具体例】
宅建業者A社が、5年以上空家となっていた築45年の一戸建て(月額賃料6万円)について、貸主・借主双方から媒介の依頼を受けたケース。
- 最大報酬額: 6万円 × 2.2 = 13万2,000円(税込)
- 貸主からのみ受領する場合: 最大13万2,000円
- 貸主・借主の双方から受領する場合: 合計13万2,000円まで
- 例①:貸主から6万6,000円、借主から6万6,000円 → OK
- 例②:貸主から11万円、借主から3万3,000円 → OK
- 例③:貸主から10万円、借主から5万円 → NG(合計15万円で超過)
【実務上のメリット】
- 老朽化・空家物件の活用が促進: 業者側も収益確保が可能となり、放置物件への対応が進む。
- 貸主負担型モデルへの対応: 借主負担を軽減しつつ、貸主から十分な報酬を得られる。
- 交渉の幅が広がる: 貸主・借主どちらからどれだけ受け取るか、柔軟に設定可能。
【注意点】
- 報酬額が通常の上限(1.1か月)を超えるため、必ず媒介契約時に特例内容の説明と同意が必要です。
- 空家等の「1年以上未使用」や「使用見込みなし」の判断には、証拠資料(登記簿や現況写真等)を保管しておくと安全です。
- 報酬の受領割合(貸主:借主)が変わる場合、その合計が必ず2.2か月以内であることを確認してください。
【背景・目的】
近年、地方部や都市郊外での放置空家の増加が社会課題となっています。
老朽化・修繕費の問題から、これらの物件は収益性が低く、仲介業者が敬遠しがちでした。
今回の改正により、宅建業者が空家を取り扱いやすくなり、貸主にとっても賃貸化が現実的になることで、空家問題の解消に寄与することが期待されています。
12. 長期の空家等の貸借の「代理」の特例
この改正のポイント: 長期間使用されていない空家等に関して代理契約を行う場合、宅建業者が貸主から借賃の2.2か月分を上限として報酬を受領できる特例が新たに認められました。
【対象となる物件】
- 長期の空家等であることが条件です。
- 具体的には:
- 現に1年以上使用されていない宅地建物
- または、将来にわたって使用の見込みがない宅地建物
【「代理」とは?】
宅建業者が依頼者(貸主)の名において契約の締結を行う契約形態です。媒介(仲介)とは異なり、業者が契約の当事者としての法的責任を伴う立場で動きます。
【報酬の上限(改正内容)】
- 通常: 貸主・借主から合計して借賃の1.1か月分が上限
- 今回の特例(代理契約):
- 貸主から最大2.2か月分まで受領可能
- 借主からの受領は不可(貸主のみから受領する形)
- または、貸主・借主の合計で2.2か月分まで受領可(例:貸主1.1か月+借主1.1か月)
【特例適用の条件】
- 代理契約を締結する際に、依頼者(貸主)に対して特例の内容を説明し、合意を得ることが必要です。
- 媒介契約の場合と同様、契約書面への明記が望ましいです。
【具体例】
宅建業者B社が、築40年・空家期間5年の戸建住宅(月額賃料:7万円)について、貸主から代理契約により賃貸借契約の締結を依頼されたケース。
- 報酬の上限: 7万円 × 2.2か月 = 15万4,000円
- この金額を貸主から全額受領する場合:OK
- 貸主・借主からそれぞれ受領する場合:
- 例①:貸主から7万7,000円、借主から7万7,000円 → OK
- 例②:貸主から10万円、借主から5万4,000円 → OK
- 例③:貸主から10万円、借主から7万円 → NG(合計17万円で上限超過)
【実務上のメリット】
- 空家活用に積極対応できる: 収益性の低い空家にも対応するインセンティブが生まれ、流通促進に貢献。
- 代理形式でも媒介と同じ特例が適用: 契約形態による報酬格差を緩和し、柔軟な業務対応が可能に。
- 貸主の希望に応じた対応がしやすい: 代理権限を得ている場合でも十分な報酬を確保できる。
【注意点】
- 説明と合意が前提: 貸主の事前同意なく2.2か月分の報酬を請求することはできません。
- 媒介と代理で報酬の上限は共通(合計2.2か月分)ですが、契約形態に応じて管理責任も異なるため、業者側の理解が必要です。
- 金額の按分に注意: 合計上限額を超過しないよう、書面での明記と社内チェック体制を整えることが重要です。
【背景・目的】
この制度は、媒介契約に加えて代理契約でも同様の報酬特例を認めることで、空家対策をより実効的に進めることを目的としています。
媒介に比べて業務責任が重くなりがちな代理契約では、十分な報酬が得られないことで取り扱いを避ける業者も多く、
本改正は制度の公平性を確保しつつ、地域の空家流通を促す観点から非常に意義のあるものとなっています。
13. 媒介報酬以外の金銭
この改正のポイント: 宅建業者が行うコンサルティング業務等に対する報酬について、媒介報酬(仲介手数料)とは別に受領することが認められるようになりました。
ただし、事前に書面で説明し、契約を締結していることが前提条件となります。
【媒介報酬とは?】
宅建業法により、売買・賃貸などの契約成立に関して、宅建業者が受け取ることができる報酬(仲介手数料)は上限額が厳格に規定されています。
これに対し、本改正では「媒介報酬とは別に、実質的に仲介とは異なる業務について、報酬を受け取ること」ができるとされました。
【対象となる業務の具体例】
以下のような不動産コンサルティング的な業務が対象になります:
- 相続に関する相談や手続支援
- リフォームやリノベーションの提案
- 空室・空き家の活用に向けた課題整理・活用アドバイス
- 空き家・空室の定期的な管理業務
- 司法書士・税理士・建築士などの専門職の紹介
- 不動産取引に関連する税金や手続きに関する情報提供
【報酬受領の条件】
- 媒介報酬とは別契約であること(例:コンサルティング契約書など)
- 報酬の額や内容を事前に書面で説明し、依頼者の同意を得ていること
- 受領の目的が明確で、業務の実態に見合った金額であること
【実務上のメリット】
- 多様なニーズに対応: 顧客からの「相続相談だけしたい」「管理だけお願いしたい」といった要望にも柔軟に応じられる。
- 収益の多角化: 仲介手数料だけでなく、コンサル業務やサービスの提供によって安定した報酬を確保できる。
- 専門性の活用: 宅建業者が保有する不動産知識を活かし、顧客満足度向上にもつながる。
【注意点】
- 媒介報酬と混同しないこと: 仲介契約に基づく通常の報酬とは別扱いであることを明確に区別しておく必要があります。
- 口頭契約は不可: 必ず報酬額・業務内容を書面で説明・明示し、契約書等に記載しておくこと。
- 金額の妥当性を意識: 不当に高額な報酬を請求すると、宅建業法違反とみなされるおそれがあります。
【背景・目的】
近年、不動産取引は複雑化・多様化しており、仲介業務だけでなく相続・税金・リフォームなど、包括的な支援を求める顧客が増加しています。
これまで宅建業法では「報酬=仲介手数料」という枠組みにとどまっていましたが、本改正によりコンサル業務などを明確に切り分けたうえで報酬を受け取ることが可能となり、不動産業者の役割がより専門的かつ多様化することが期待されています。
法令上の制限:建築基準法の法改正(4号建築物の見直し)
この改正のポイント: 小規模な木造建築物に関する「4号特例」が見直され、建築確認や構造審査の対象範囲が拡大されました。特に、延べ面積200㎡を超える木造建築物は、新たに「2号建築物」として審査が義務化され、審査省略制度の対象外となりました。
1. 改正前の制度(旧4号建築物)
- 対象:木造2階建て・木造平屋建て(いわゆる4号建築物)
- 都市計画区域・準都市計画区域内では建築確認が必要
- 審査省略制度(4号特例)が適用され、建築士の設計であれば構造審査などが省略可能
2. 改正後の分類(令和の新制度)
従来の「4号建築物」が、延べ面積200㎡を境に2つの新カテゴリーに再編されました:
① 新2号建築物(200㎡超)
- 対象:木造2階建て・木造平屋建てで延べ面積が200㎡を超えるもの
- 全ての地域で建築確認が必要(従来は区域限定)
- 大規模な修繕・模様替えも確認対象
- 審査省略制度の対象外(構造・省エネ関係図書の提出が必要)
② 新3号建築物(200㎡以下)
- 対象:木造平屋建てで延べ面積が200㎡以下のもの
- 都市計画区域・準都市計画区域内に建築する場合は建築確認が必要
- 審査省略制度(4号特例)が引き続き適用
3. 審査省略制度(4号特例)とは?
4号特例とは、小さな木造建築物を建てる際に、建築士が設計していれば構造関係の審査を省略できる制度です。今回の改正により、特例が適用される範囲が狭まりました。
4. 比較表(改正後の扱い)
| 建築物の種類 | 建築確認 | 審査省略制度の適用 |
|---|---|---|
| 特殊建築物(200㎡超) | ○ | × |
| 大規模建築物 | ○ | × |
| 木造2階建て・平屋建て(延べ面積200㎡超) (新2号建築物) |
○ | × |
| 木造平屋建て(延べ面積200㎡以下) (新3号建築物) |
○(都市計画区域等内) | ○(4号特例適用) |
5. 実務上の注意点
- 延べ面積200㎡を超える木造建築物は、構造関係規定および省エネ関連図書の提出が必須。
- 都市計画区域外であっても、新2号建築物であれば確認申請が必要。
- 建築士が設計していても、特例が使えないケースが増えているため、設計・施工前に確認申請の要否をしっかり判断する必要があります。
6. 背景と改正の目的
木造住宅の多様化・大型化により、構造安全性や省エネ性能のチェックを徹底する必要性が高まってきました。
これまでの「小規模=簡易審査」という考え方を見直し、安全性確保と脱炭素社会の実現に向けて、確認手続の基準が整備された形となります。
建物:筋交いの緊結方法に関する法改正
この改正のポイント: 木造建築物における「筋交い(すじかい)」の取り付け位置について、より厳格な規定が設けられました。これにより、構造上の安全性、特に耐震性の向上が図られます。
1. 改正前のルール
- 筋交いは、その端部を柱や梁(横架材)の「仕口に接近した位置」で、ボルト・かすがい・くぎなどの金物で緊結すればよいとされていました。
- つまり、「仕口そのもの」ではなく「その付近」に取り付けてもOKでした。
2. 改正後の新ルール(令和改正)
- 筋交いは、両端を柱または梁等に、金物でしっかり緊結しなければならない。
- そして、少なくとも片方の端部については、柱と梁が交わる「仕口(しぐち)」の部分そのものに緊結することが義務付けられました。
- これにより、「仕口付近」→「仕口そのもの」への緊結というルールに明確に変更されました。
3. 「仕口」とは?
仕口(しぐち)とは、木造建築において柱と梁・桁などの構造材が交差・接合する部分を意味します。建物全体の構造強度を支える重要なポイントです。
4. 【要するに】簡潔にまとめると
- 改正前:「仕口付近に緊結」でOKだった
- 改正後:「仕口そのものに緊結」が義務化
- かつ、両端とも柱または梁に金物で緊結する必要あり
5. 改正の背景・目的
この改正は、耐震性の強化を目的としたものです。
従来の「仕口付近」への取り付けでは、地震時に緩みやすく、筋交いの本来の耐力を発揮できないリスクがありました。
そのため、構造上もっとも力が集中する仕口に直接緊結することを義務づけることで、住宅の安全性をより確保する制度へと改正されたのです。
6. 実務上の注意点
- 設計図作成時に、筋交いの緊結位置が「仕口そのもの」であるかを明確に記載する必要があります。
- 施工現場では、金物の種類・位置・取付方法に関する建築確認検査や完了検査での指摘対象となる可能性があります。
- 建築士・工務店・施工管理者すべてがこの改正内容を正確に理解しておくことが重要です。