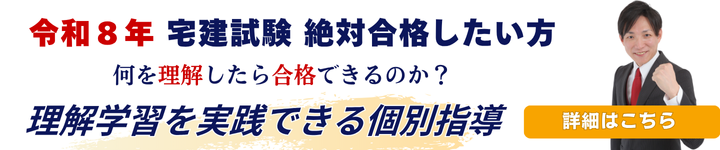おはようございます!レトスの小野です!
『勉強は下りのエスカレーターを上るようなもの』
今日勉強しても、数日勉強しなかったら、忘れてしまう。
勉強して1段上がっても、数日経ったら、もとの場所に戻ってしまう。
「忘れる」という下りのエスカレーターよりも早く「上る=勉強する」必要があるわけです。
そして、何度も復習すれば下りエスカレーターの速度もドンドン遅くなってきます!
これは、頭に定着してきている証拠です。
ここまでたどり着くには、半年以上時間がかかります。
だからこそ、今しっかり勉強しておく必要があるわけです!
試験半年前から勉強して合格できる人は、
受験生の数%ほどです。
私自身、この数%に入れる程記憶力は良くありません。
だから、12月毎日勉強していました!
自分自身記憶力が悪いと知っていたからこそ
この時期から開始したわけです。
もし、あなた自身、暗記が苦手と思っているのであれば、
今から本格的に理解学習を実践していきましょう!
暗記が苦手であれば、そうでもしないと、合格するのは難しいです。


【問1】時効
AはBに100万円を貸した。
そして、AC間で保証委託契約が結ばれた。
時効期間の経過前に、Bが債務を承認した場合、Bの時効は更新するが、保証人Cの時効は更新されない。
>>折りたたむ
【解答】
X
債務者が債務を承認すると、債務者だけでなく
保証人の時効も更新します。 つまり、BもCも時効は更新します。
「時効の更新」とは、時効期間がスタート地点(ゼロ)に戻り、1からスタートし直すことを言います。
これは、保証債務に「付従性」があるからです。
この問題のポイントは上記だけですが、
これを理解するためには「保証の性質」など複数のことを理解する必要があります!
不合格者の多くは複数の分野が絡む複合問題を苦手としています。
これを克服しない限り、合格できません。
こんな複合問題も個別指導では基本から一歩ずつ教えていきます!
↓↓
https://takken-success.info/lp/lpp/
【問2】業務上の規制
甲県に本社、乙県に支社を有する宅建業者A社が、
本社、支社ともに宅建業を営んでいる場合、
従業者名簿については、本社、支社それぞれに備え付けなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
〇
事務所ごとに業務に関する従業者名簿を備え付けなければなりません。
一括して本社に備え付けておくことは宅建業法違反となります。
■あと、事務所に備える物って何でしたっけ?
覚えていますか?
・標識
・報酬額の掲示
・帳簿
・従業者名簿
・専任の取引士
ですね!
全て覚えてくださいね!
【問3】建築基準法
用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し、都市計画において定められた数値以下でなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
X
用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し、当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めます。
本問の「都市計画で定められた」という記述が誤りです。
これはどういうことか?
なぜそんなことをするのかイメージできるようにしましょう!
「個別指導」では、なぜこのようなルールがあるのかまで解説しています!
理解できればそれほど難しくはありません!
▼個別指導の詳細はこちら
↓
https://takken-success.info/lp/lpp/